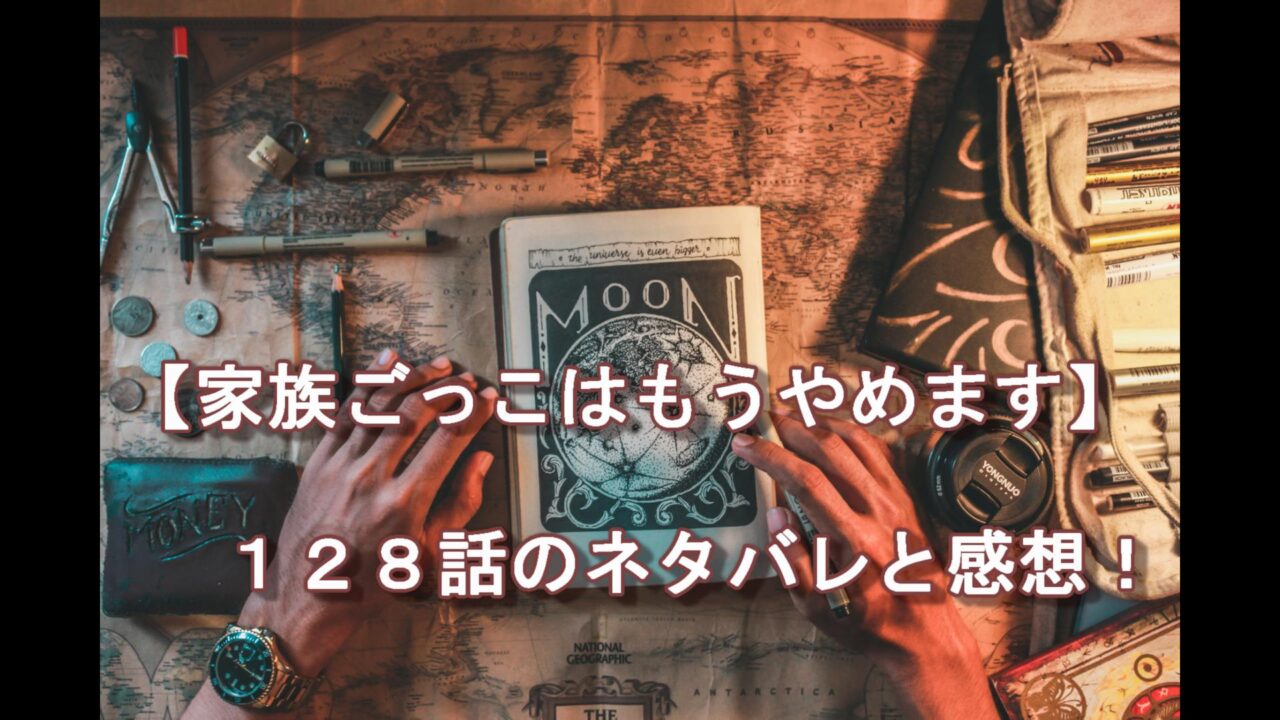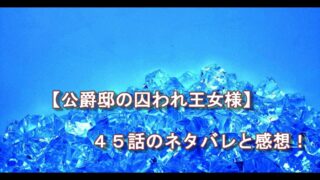こんにちは、ちゃむです。
「家族ごっこはもうやめます」を紹介させていただきます。
今回は128話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

128話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 異変②
「あの、殿下・・・」
ヴィヴィアンは不安に耐え切れず、アレスを呼んだ。
彼が自分が知っている上品できちんとしたアレスであることを願って。
アレスは片方の口元を上げる。
「ここは出入りが統制されているが、どうやって来たんだ?」
「それが、殿下に申し上げたいことがありまして・・・」
「ああ」
アレスは分かるような表情で話した。
「お前のそばを守って他の貴族たちを押さえつけるつまらないことに参加しろと?」
「・・・」
ヴィヴィアンは唇をかんだ。
「私は素直な女が好きだ、ヴィヴィアン」
彼が惜しいという表情で話を続ける。
「私にうるさくふるまう女はあまり好きじゃない」
ビビアンは一瞬、怒りがこみ上げた。
「じゃあ、ナビアさんは?あの女は従順でしたか?」
アレスはにっこり笑う。
「彼女は特別だ」
「何がそんなに特別なんですか?外見?能力?家?そんなことは私も見劣りしません!」
「お前は神の妻になるにはあまりにもつまらない」
その言葉にヴィヴィアンはビクッとした。
「神の妻・・・?」
アレスはヴィヴィアンの首をつかみ、さっと持ち上げた。
「カッ!カッ・・・!」
「ただの虫にも劣る人間にすぎない」
相手にすることさえ面倒くさそうに退屈そうな目つき。
ヴィヴィアンはかろうじて彼の手の中を離れ、全身を震わせた。
「あなた、皇子殿下じゃないんですよね・・・?殿下はこんなはずがありません!」
アレスは面白い言葉を闇いたという表情で笑い出した。
「間違った言葉ではないかもしれない。私はアレス・ダフマン皇子であると同時に神でもあるから」
彼は目を光らせて言った。
「私はニラトだから」
ヴィヴィアンは言葉が途切れ、正確に聞き取れなかった。
しかし聞こえなくても不気味さは感じる。
とても不吉でひどい名前に違いない。
ヴィヴィアンは後ずさりして倒れた。
狂いそうな恐怖が全身を蚕食し、身動きもできない。
「助けてください・・・!」
「心配しないで、ヴィヴィアン。私は慈愛に満ちた君主だから、私が治める家畜を大事にしてあげるから。しかし、言うことを聞かないものは厳重に罰しなければならない」
彼はヴィヴィアンの髪をつかんだ。
ヴィヴィアンは悲鳴をあげながらもがく。
這ってでも逃げようとする必死のもがきだった。
しかし、いつの間にか動作が止まった。
彼女の白目が真っ黒に染まったのだ。
間もなくビビアンが変なことを言った。
「偉大なるアレス皇帝陛下万歳」
精神が汚染されたのだ。
アレスはその姿を見下ろし、肩を小さく揺らし、次第に大きく笑い出した。
「ハハ!」
これが力だ!
これこそが無所不為の真のカであり、自分がこの力の主であった!
彼がどこかを凝視する。
「もうお父さんを寝室に移したみたいだね」
さっき、異界の怪物たちをすべて撒き散らして、誰も城の外に出ないように防いでおいた。
皇居にいる者は、すべてヴィヴィアンのように精神を支配されるだろう。
帝国の次の皇帝はアレス皇子殿下しかいない。
偉大なその方に従わなければならない。
これは単なる精神支配ではない。
神の権能で彼らの精神に恐怖を与えるのだ。
そのようにすべての作業を完了すれば、いつ何があったのかというように、皆飲み過ぎたようだと混乱するだろう。
儀式の基底には「アレスが皇帝になるべきだ」という考えが敷かれたまま。
アレスは残念そうに舌鼓を打った。
「この力を思う存分使えないのが一番残念だ」
外部の神はここに属さない神であり、既存の神々と対極点に置かれている。
この程度の力を使うのもかなり無理なことだった。
「でも、これくらいなら絶対にバレるはずがない」
もし彼の力が土着の神々に発覚したら困難だった。
そうなると、また別の体を探して乗り換えなければならないから。
「<ぅ!」
アレスは頭をつかんで苦しそうなうめき声を上げる。
「私は今、何を考えたんだろう?」
今、自分ではないような変な考えがふと浮かんだようだった。
何だと思ったのか内容は思い出せなかった。
ただ妙な気持ちだけが脳裏に残っているだけ。
「・・・急に力を大きく放出して混乱したのかな?」
このようなことがあったので、アレスはすぐに大したことではないと思った。
こうすれは必ず補償のように自分が持つ力がさらに大きくなったためだ。
おそらく成長痛のようなものだろう。
頭痛はすぐ消え、やはり神格は一層鮮明になった。
アレスは長い息を吐き出し、満足そうにつぶやく。
「もう宴会場に行ってみようか?」
彼の目はさらに濁っていた。
皇帝の寝室に入る前、ナビアは突然の悪臭に目をぎゅっと閉じて鼻と口を塞いだ。
「お姉さん?」
クリードは心配そうに彼女を見下ろす。
ナビアは嫌なにおいで吐き気がした。
しかし、クリードはこの匂いを全く感じない表情で平穏に見えた。
「これさえも私にだけ感じられるの?どうして?)
汚物のにおいではなく・・・そう、死体が腐る匂いだ。
彼女は死体の腐る臭いを知っていた。
6回目で生け贄として野蛮族に売られた時、飽きるほと嗅いだにおいだったからだ。
ところで、ここでどうしてそんな匂いがする?
ナビアはしかめっ面をして皇帝の寝室を見た。
寝室は広々と開いている。
「お姉さん、大丈夫?」
「何でもないわ」
ナビアは首を横に振りながら彼の手を引いた。
中に入ろうという意味だ。
クリードはまだ彼女の手に握られていたが、心配を拭うことはなかった。
寝室の中は皇帝とダイアナ以外は誰もいない。
それがおかしかった。
皇帝が危急なのに議員と宰相はもちろん、彼の安危を保護する騎士さえいないと?
ナビアの目が細くなった。
(全く思いもよらない方向に事が進んでいるようだ)
寝室の中に入ると、死体の腐る臭いがさらに強く漂った。
しかし、どこにも死体はない。
念のためユリッヒを見た。
彼は目を開けていた。
ただ、焦点もなく死んだ魚のような目だ。
いずれにせよ、まだ死んだわけではない。
(皇帝が元気になれば、尻尾を踏むことができるだろう)
そのしっぽの核心は、見るまでもなくダイアナだったはず。
ナビアは皇帝に近づき、彼の体に手を当てる。
「百月」が反応しなかった。
(どうして?)
ナビアは再び百月の力を引き出した。
今まで百月が治癒できなかった病気はない。
今は何か手違いがあったのだろう。
しかし、百月は最後までユリッヒに反応しなかった。
それなら理由は二つだ。
一つは百月を使う必要がない状況、だから死んだか病気がないことだ。
もう一つは神に関わる力で苦しんでいるということ。
ユリッヒは明らかに元気がなくなってきている。
だから問題があるのは確かだった。
(それならやっばり・・・)
ナビアはゆっくりと頭を上げる。
ダイアナと視線が合った。
彼女は笑っていた。
「何がうまくいかないの?」
ファアアッ!
言葉が終わると同時にクリードが強力な保護膜を生成する。
半透明のミルク色の保護膜越しに皇后は正確にナビアを凝視していた。
(透明化魔法で姿を消しているのに、どうしてそんなことができるの?)
ダイアナは魔法使いでもなかった。
彼らは透明化魔法が役に立たないという事実に気づき、無駄な魔力の浪費を減らそうと姿を現した。
ナビアは皇帝から手を引いた。
「・・・神と契約したんですね」
皇帝は平凡な毒のようなものにやられたのではない。
ダイアナはにっこり笑った。
「なるほど、お前に何かあると見当はついていたんだ。本当にいろいろと特別な子なのね」
彼女の覗線はすぐに敵慣心をむき出しにしているクリードに向けられた。
「あの子は化身ではないはずなのに、今何ともないのを見ると、どうもお前が何かしたんだよ。どんな神と契約したのだろうか?土着の神様の一つなんでしょうけれども」
その言葉からナビアは1つ推測できた。
相手が契約した神は外部の神だろう。
そうでなければ「土着神」という表現を使うはずがないから。
(外部の神の存在を知っている人自体がほとんどいない。あっても、この世界の神を土着神とは表現しない)
外神は非常に強力な力を持っていたため、全身が緊張に染まった。
もちろん、彼らにもレベルがある。
たとえば、ラルクが契約した外部神を例に挙げると、その存在は万稗殿の頂上にある神だ。
おそらく、それだけの位置の存在と契約するのは容易ではないはずだから、下位格の神のはず。
(クリードがまともな理由が私のせいだというのはどういう意味だろうか?それでは化身でない人は今危険な状況ということだろうか?)
ナビアの表情はこわばった。
今日の勝利宴会は類例のない巨大に行われていたので、あらゆる貴族が皆集まっている。
宴会場で消息を待っている貴族たちに何をするためにこんなことを企てたのか?
(でもそんなことなら皇后がこの席を守っている理由がないじゃないか?)
ナビアはその時やっと気づいた。
「アレス皇子が化身なのですね」
「ふ一ん、よけいに頭が回るようね」
クリードはナビアを守るように腰を抱えながら自身のところに引き寄せた。
彼の両目は敵意でめらめらと燃えている。
「それじゃ、あなたは化身ではなく、普通の人だと?」
ピン!
クリードは鋭い鋭気を帯びた魔力の槍を召喚した。
ダイアナは凶悪な武器を前にしても全く怖がらなかった。
むしろ笑い出した。
「ハハハ!愚かなこと」
彼女の全身から不気味なエネルギーが流れ出る。
ナビアは嫌なにおいの源がダイアナであることに気づいた。
「なんであなたから死体が腐る臭いがするの?」
ダイアナの目はその言葉に狂気の目で輝いた。
彼女の笑顔は以前のように魅惑的ではなく、ただの狂人のようだった。
「1000人の命を代価に神と契約したのがまさに見た後だから!」
「1000人?人を生け贄にしたと言っているのですか?」
化身契約に1000人の命が必要なのはなぜ?
そして、なぜ神と契約したのがアレスではなくダイアナなのか?
何も理解できなかった。
この状況は確かにおかしかった。
理解するにはダイアナの記憶を読むのが一番早いようだ。
(精稗支配魔法を使ってみよう)
すぐに魔力を引き上げると、魔力が皇后の精神と感応した。
幸いにも彼女の記憶が滑らかに読まれた。
ダイアナは1000人の人間を犠牲にして身上に血をまき、そこに外部の神を降臨させた。
それで彼女は神の力を借りて呪いを使えるようになったのだ。
呪いの対象はユリッヒ。
『時が来るまでゆっくり乾きなさい。そうして決戦の日になればあなたの命をおさめるだろう』
それで終わりではなかった。
アレスがした契約がおかしかった。
(これは化身契約ではない。外神が直接アレスの体に入ったんだ!)
「あなた、何をしたの!」
記憶を読み終えたナビアが激しく叫んだ。
ダイアナの記憶を読んで、今日何をしでかすかも全部分かった。
アレスは、いや、アレスの中に入っている外部の神は、今日の人間の頭の中にすべて浸透し、彼らの恐怖を吸い取って体を大きくするだろう。
彼らは世の中を混乱に陥れるつもりだった。
ダイアナは不気味な笑みを浮かべて言った。
「完璧な君主が治める楽園が誕生するだろう」
そのためには先行しなければならないことがある。
「私を裏切ったこんな人間はもういらない」
ダイアナは焦点のない目でぼんやりと空中を凝視しているユリッヒをじっと見つめた。
「アイルツ公爵家を皆殺しにして、あなたにあんなに多くの利盆を与えてくれたのに、返ってきたのはごまかしで平民の女を皇室にかける裏切りだなんて。本当に酷いじゃないかしら?」
ダイアナは自分の罪について何も考えていなかった。
ただ自分が受けた不当さだけを吐露するだけ。
「あなたのような人間は皇帝になる資格がない!消えろ!」
ユリッヒはダイアナに首を絞められた瞬間理性が戻ったのか、瞳に焦点が当てられた。
そうしても彼にできることは何もない
全身に生れとは一つもなく、ダイアナの力すらかなわなかった。
何とかして生きようともがいていたユリッヒがクリードを発見した。
「く、り・・・があ!」
クリードは目の前がくらむような激しい怒りに襲われた。
母親を殺した仇敵たちが最後まで利己的にふるまう姿が気持ち悪かった。
すぐにあの二人をずたずたに引き裂いて罪を問いたかった。
アレスの体を依代にして外部神が現れたのですね。
ユリッヒ皇帝に同情する部分は一つもありませんが、こんなに呆気ないとは・・・。