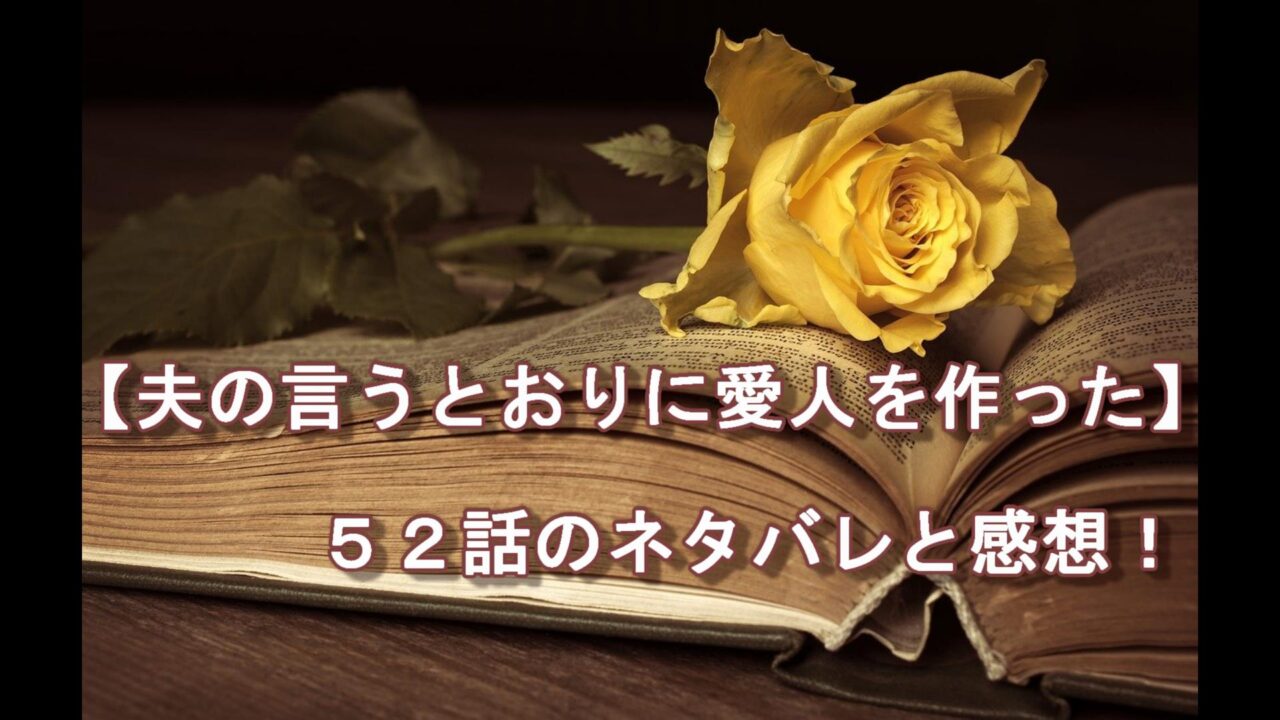こんにちは、ちゃむです。
「夫の言うとおりに愛人を作った」を紹介させていただきます。
今回は52話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

52話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- セルベニアでの出会い
結局、マクシオンは森を離れるまで目を覚ますことができなかった。
アイレンに入るやいなや、ヘンドリックがマクシオンの代わりに城に向かって騎士団が入城
したという便りを知らせる。
皇帝の命を受け、出征した廃太子の騎士団。
セルベニアの立場ではこれほどの招かれざる客もいないだろうが、だからといっていい加減に対応することもできない。
地元の人々が騎士団をちらりと見る。
彼らの視線には外地人に対する恐怖と好奇心が混じっていた。
「一様に疲れた顔ですね」
「首都を離れて久しいのでセルベニアの状況を知らなかったのですが、少なくとも以前のような雰囲気ではないのですね。前に立ち寄った時は、これほど静かな村ではありませんでした」
「殿下、戻りました!」
ヘンドリックはエドワードの元に戻る。
セルベニアの葉っば模様が描かれたローブを着た男を同行させたままだった。
「リンデマン大公殿下、むさくるしい所を訪ねてくださって光栄です。私はカッセル・ディ・セルヴェニア・アイレン侯爵の補佐官であるデス・ディ・エアロベン男爵です。状況はクローデン子爵から聞きました。まず城に移動した方がいいと思います」
「歓迎してくれてありがとうございます」
騎士団はセルベニア城に向かう。
ルイーゼは不思議そうな顔でエアロベン男爵の言葉をかみしめた。
「クローデン子爵?」
「ああ、私の名前です」
ヘンドリックは平気な顔でルイーゼに近づきながら言った。
「ヘンドリックは貴族だったのですか?」
「はい。正確にはヘンドリック・デ・クローデン子爵です。領地はなく、爵位を維持するだけの貴族ですが」
「なんてこと、知りませんでした」
「団長と副団長を除いて、騎士団内の数少ない貴族出身です。気楽に接してください」
彼の言葉にルイーゼの顔にもっと大きな混乱が浮かんだ。
「マキシオンはマキシオンだけど?」
「え?まさか知らなかったんですか?」
ルイーゼの表情の変化にヘンドリックが信じられないという顔をした。
「副団長はなんとカリオドの唯一の血筋じゃないですか!」
「カリオドですか?」
カリオドといえば、ルイーゼも知っている家門だった。
北部の三大家門、リンデマン、カリオド、ベオデン。
そのうち、北部で最も裕禰な領地を持つリンデマンの唯一の嫡子が皇后の座に上がり、皇子を産むことになり、リンデマンの爵位は自然に皇太子に継承された。
エドワードに残った唯一の姓が「リンデマン」である理由もそのためだ。
その次がカリオド。
カリオドの領地は、南部と北部を区分する広い荒野を通り過ぎるやいなや、一番先に登場するリンデマンの領地とは異なり、より高い位置にあり、北部でリンデマンより広い領地を持つ家門だった。
漁業を主にするため、船乗りがほとんどであることで有名だ。
でも・・・。
「マクシオンはライ麦パンとニシンも食べないんですよ。カリオドはニシン料理が有名ではないですか?」
「私もその点が不思議だったのですが、あまりにも幼い頃にたくさん食べて飽きたとおっしゃっていました」
「なんてことだ」
「社交界の人の中には知らない人はいないと思っていました。それがあまりにも大きなスキャンダルだったので」
ルイーゼはぎこちなく笑う。
社交界で活動していないヘンドリックと団員たちの目には、ルイーゼは社交界の有名人の一人に見えただろうが、実状はただレイアードの後ろに垂れ下がった影に過ぎなかったからだ。
誰も彼女と話したくなかったので、このような話を教えてくれる人は当然いなかった。
マクシオン本人やエドワードを除いては。
エドワードは本人の話ではないので話を切り出すのが難しかったとしても、マクシオンが今まで言ってくれなかったのはルイーゼも少し寂しかった。
「マクシオンについて誰よりもよく知っていると思っていたのですが・・・違ったようですね」
「ははは、大切な人ほど彼に隠したい過去があったりしますからね。副団長はそのような気持ちだったのではないかと思います。細かい話は目が覚めたら直接聞いたほうがいいですね」
「はい、そうしなければなりません」
ルイーゼは複雑な顔でうなずく。
騎士団はすぐに城に到着した。
セルベニアの城は有名に比べて規模が小さい方だ。
全体的に地味な感じがする平凡な城だったが、領地を巡る城壁から内部の壁、門、構造が全て敵が攻め込めば、いつでもすぐに対応できるよう実用性を強調したところだった。
エアロベン男爵が団員たちは別館に、エドワードとマクシオンは本城に案内する。
「ヘンドリック。団員たちを頼むよ」
「はい」
自然に団員たちと別館に向かおうとするルイーゼをエドワードが呼び止めた。
「ルイーゼさん、お父様のブローチはお持ちですか?」
「あ、はい。出征以来、いつも内ポケットに入れています」
「では早速会ってみるのもいいですね。帰りに間いたニュースですが、現家主のカッセル・ディ・セルベニア侯爵が病中で、今彼の母親が代理で家を管理しているそうです」
「その方のお母さんなら、私には叔母になる方でしょうか?」
「はい。セルヴェニアが皇室と親しい時代に何度かお会いしたことがありますが、とても厳しい方でした。ルイーゼさんが最初から単独面談をするのは難しいかも知れないですから」
「ありがとう。一緒に行きましょう。それにしても厳格な叔母さん・・・聞いたことがあるような」
ルイーゼがじっくり考えている間、セルベニアの使用人たちが担架を持ってきて、荷車からマキシオンを取り出して横にする。
あまりにも巨体で担架の外に手足が突き出たが、使用人たちは平然とした顔で彼を移した。
エドワード、ルイーゼ、エイロベン男爵が本館の正門に入る。
そこにはエドワードの言う通り、顔から厳格さがにじみ出る中年女性が立っていた。
白金髪に暗い緑色の瞳を持った彼女はじっと立っているだけだったが、まっすぐ伸びた首と乱れることのない姿勢が完璧に貴族的だ。
「訪問を歓迎します。エドワード・E・フォン・リンデマン大公殿下」
「ご無沙汰しております。ロレイン・ディ・セルベニア夫人」
「・・・ええ」
品位が感じられる言葉だったが、表情と返事で嬉しくないという雰囲気が漂っている。
ロレインの視線はルイーゼに移った。
「お会いできて嬉しいです」
「あ、こんにちは。ルイーゼ・ディ・セルヴェニアと申します」
「セルベニアですか?」
「はい。大公殿下に父がセルベニアだったことがあったと聞きました。アレン・ディ・セルヴェニアです」
彼女は腕の中からブローチを取り出す。
手のひらほどの大きさの銀製ブローチの中央には、セルベニア家を象徴する葉っば模様が彫られていた。
「ルイーゼ・・・まさかあのルイーゼ?」
ロレインは目を見開いて尋ねる。
「私のことを知っているのですか?」
「なんてことだ。あなたのお父さんが私の話をしたかどうか分からないね。私はロレイン・ディ・セルヴェニアよ。あなたのお父さんと首都のセルベニア治療士養成アカデミーの同期だよ。気楽に叔母さんと呼びなさい」
満面の笑みを浮かべたロレインの声に隠すことができなかった歓喜がにじみ出た。
ルイーゼがやっと思い出したという顔で口を開く。
「あ、そうだ。女の子が大好きなロレインおばさん」
「あなたのお父さんがそう言っていた?」
「はい。実家の家族の中で、私の存在を唯一知っている方だとも付け加えてくれました」
「間違った言葉ではないが。あいつは最後まで気に入らないわね。ところで、ルイーゼ、私があなたにどれだけ会いたかったか知ってる?」
ロレインは明るい顔でルイーゼに近づく。
「私が余計な心配をしたようだが」
彼らを見て、エドワードは低い声でつぶやいた。
マクシオンも貴族だったのですね。
城で叔母と出会ったルイーゼ。
彼女の過去も少しずつ判明するのでしょうか?