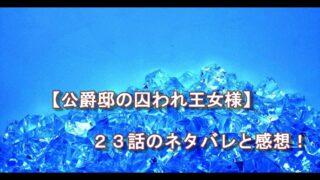こんにちは、ちゃむです。
「継母だけど娘が可愛すぎる」を紹介させていただきます。
今回は302話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

302話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 魔女裁判
法廷は類を見ない満員だった。
まだ裁判が開かれるまではかなり時間が残っていたが、傍聴席は数多くの人で賑わっていた。
王族が裁判台に上がるのは非常に珍しいこと。
その上、その罪状がさらに奇異なので、人が集まるしかなかった。
魔女疑惑。
王妃が魔女裁判を受けるという話に誰かは驚愕を、誰かは肯定を、誰かは弁護をしたが、皆が混ざり合うとただの騒ぎだった。
その騒ぎは遠くの待合室にまで及んだ。
カリンは息をのんだ。
すでに数日前から息が詰まりそうだった。
「なんでこうなっちゃったんだろう」
アビゲイルのおかげで命を救われたあの日。
カリンは自分がドレスルームに何を持ってきたのか、後になって分かった。
その赤い靴が通りかかった場所には火がついた。
噂に火がついて、父が火を大きくして、大きくして、大きくして・・・。
その時ドアが開く音が聞こえ、カリンは驚いてドアのそばを見る。
ストーク公爵がいた。
彼の顔は太陽の下でただただ明るかった。
「カリン、ここにいたんだ。もう行こう。証言を準備しないと」
彼の顔はとても爽やかで、カリンはむしろ鳥肌が立つ。
彼女は席を立つかと思い、すぐにストーク公爵の前にひざまずいた。
崩れるような泣訴だ。
「お父様、どうか私の頼みを一つだけ聞いてください。お願いします」
カリンは公爵のズボンの裾を掴む。
命綱でも握るように手がぶるぶる震えてきた。
「どうか裁判を取り消してください。虐公爵に嫁いでもいいです。お父様の言うことなら何でも従います。だからお願いします」
カリンの肩は一瞬にして崩れる。
いつも孤高に腰を伸ばしていた令嬢が、乞食のようにひざまずいて哀願していた。
父親の言葉に反抗せず、いつも従順だったカリンだった。
こんなに面と向かって父の意に逆らったことは一度もない。
「王妃様が廃位になるだけでなく、死ぬかもしれません。だからお願いです・・・!」
自分についた火を消してくれた人に火をつけることはできなかった。
ストーク公爵は驚いた目でカリンを見て、片膝をつく。
「カリン、私の娘よ」
カリンはその声がとても優しくて頭をもたげた。
彼は彼女の頬を声と同じくらい柔らかい手で撫でる。
「王妃が死ぬのではないか心配なのか?」
彼女は急いでうなずく。
父親の優しさに、カリンはようやく息抜きができるようだった。
アビゲイルが手を捨てて自分を助けてくれたことは父親もよく知っている。
自分の娘を助けてくれた女性を殺すはずがない。
追い詰めるはずがない。
いくらお父様でも、そんな・・・。
「そもそも殺そうとする裁判なのに、なぜ私が取り消すのか?」
刃物で刺されたような気分だった。
希望に浸っていたカリンの顔が一瞬にして破片に散らばる。
公爵は冷たく席を立った。
その力に勝てず、カリンがふらついて倒れてしまったが、ストーク公爵は冷たく娘を見下ろすだけ。
「お前がどうしてこうするのか分からないな。いまさら怖がっているのか?」
「いいえ。私は・・・!」
「君はただ私の言葉に従えばいい。もう王妃になる準備さえすればいいんだ、カリン」
カリンは父親を理解することができなかった。
理解したくなかった。
自分が王妃になることがそんなに重要なのか。
たかがそんな理由で、どうしてあの善良な人を殺そうとするのか。
「こうしても殿下が私と結婚するはずもないんです!それなのに、いったいどうして!?」
カリンは大声で叫ぶ。
両目には憎悪が光っていた。
十数年間積もってきた怒りは強烈な色彩を含んでいる。
公爵はその反応に一瞬戸惑ったようだったが、すぐに平静を取り戻した。
彼はぞっとするほど冷淡な顔で答える。
「そうだね。君がお嫁に行けないかもしれない。しかし、王妃を引き下ろすだけで、他の手段があるので構わない」
カリンはぼんやりと父親を見た。
今目の前にいる男は、見ず知らずの他人のようだった。
そんな中、声だけがはっきりと聞こえてくる。
「殿下が魔女に取り憑かれ、国家を統治するほどの状態ではないと主張すればいい」
王位から引きずり下ろすのは少し大変だろうが、現在不満を持つ貴族が多いのでできないこともない。
ストーク公爵はにっこりと笑いながら話し続ける。
「そうなれば、次の王位継承者はブランシュになるだろう。まだ幼い年だから、摂政が必要だろうね」
「ま、まさか・・・」
カリンの顔は真っ青だった。
自分の父の内心がこんなにも黒いとは思わなかったのだ。
彼は満面に笑みを浮かべる。
「そうだ。私がこの国の摂政になるのだ」
重い拳で頭を殴られたような衝撃。
自分の父の貪欲さをよく知っていると思っていたら、それは傲慢だった。
「反逆を起こすつもりですか?」
「反逆ではない。忠臣としての道理を尽くすのみだ」
忠臣という単語が、こんなに汚水のような匂いを漂わせることができるのを初めて知る。
胸がむかむかするほどだった。
「魔女がこの国を害そうとするから、防がなければならないのではないか」
当事者はその悪臭を嗅げないのか、図々しい顔のままだ。
カリンがぼんやりと眺めている間に、ストーク公爵が部屋を出ていく。
彼の顔は満足感に満ちていた。
摂政。
自ら声を出して発音してみると、さらに胸がいっぱいになる。
公爵としても反逆まで起こしたくなかった。
しかし、セイブリアンが再婚を許可しなければ仕方がない。
危険負担を負うしかない。
「それでも少なくともアビゲイルを廃位させることができるから、それで満足しよう」
彼女が宮を出てくれれば、当分は安らかに眠ることができるだろう。
彼は熟睡を期待して法廷に向かう。
入るやいなや感じられる法廷の騒々しさがあまりにも愉快だった。
「この裁判は勝つしかない。最高裁判事もやはり私の味方だから」
最高裁判事は生真面目な貴族で、人魚との交流に不満を持った者。
長い間、王室のために働いてきた人でもある。
味方につけるのに時間が少しかかったが、最高裁判事も王妃のために王が取り憑かれた可能性を認めてしまった。
証拠も証人もすべて用意してある。
もう魔女の首を握ればいいだけ。
その時、侍従の叫びが聞こえてきた。
「国王殿下と王女様が入廷します!」
血のように赤いベルベットのカーペットを踏みながら、セイブリアンが姿を現した。
ただでさえ剣のような鋭い男なのに、今日に限ってたくさん刃が立っている。
そして焦っているように見えるブランシュが、その後に続いた。
アビゲールが作ってくれたベルベットのワンピースを着て。
足音もなく、重い静寂が沈んだ。
二人が上座に座ると、もう一度侍従が口を開く。
「王妃様が入廷します!」
緊張で色づいていた空気にちょっとしたざわめきが混ざり合った。
そのざわめきからアビゲールが足を踏み入れる。
彼女は地味なエンパイアドレスを着ていた。
象牙色の裾が長く引っ張られた。
魔女にしては実に似合わない服だ。
それでも人々の視線が針のように突き刺さることを感じることができた。
彼女はセイブリアンとブランシュの視線も感じることができた。
自分と同じくらい二人も不安だろう。
彼女は上座に向かって微笑んだ。
すると、人々は小さく囁いた。
「魔女裁判を受けに来て笑っているなんて」
「無実なら、あんなに平気なわけにはいかないだろう」
「本当に魔女みたいな姿じゃないか」
アビゲイルはその囁きを無視しようとした。
彼女が被告席に座ると、すぐに裁判官たちが現れる。
騒々しい雰囲気が一瞬にして静まった。
最高裁判事がストーク公爵に視線を向けると、公爵が席から立ち上がって軽く首を整えた。
「こうして裁判を要請することになったのは、数日前に宮殿で起きた不詳事の真相を把握するためです」
あらゆる薄暗い色をキャンバスに注いだように、場内の雰囲気が暗かった。
公爵は空気を吟味しながらゆっくりと話し続ける。
「王妃様が生き返った後、その後に奇妙なことが起きています。王妃様が死んだ殿下を蘇らせ、その後殿下が別人のように行動することは、皆が感じたはずです」
ついに裁判が開始されました!
現状ではストーク公爵が圧倒的有利のように思えます。