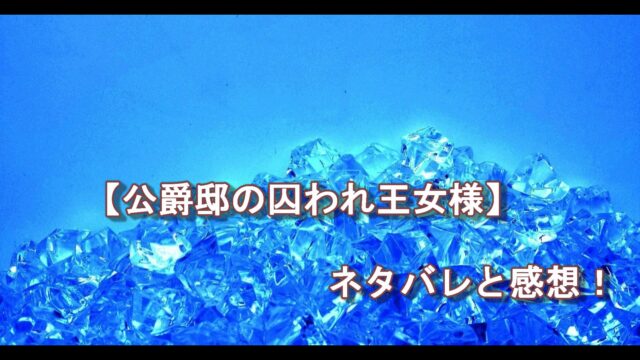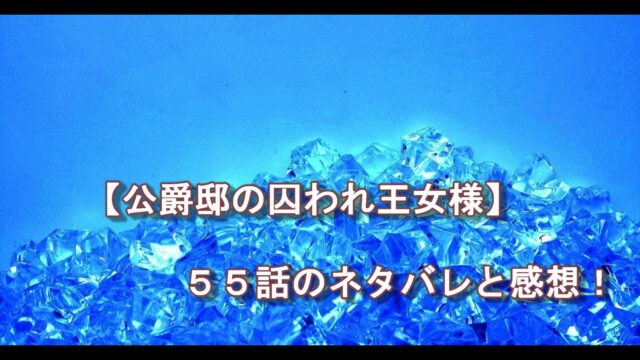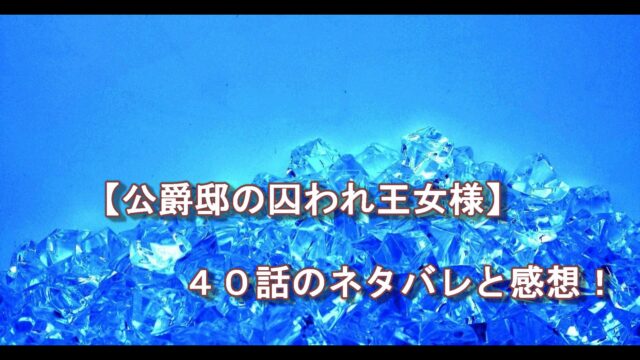こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

92話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 贈る花③
「……王子はクノー家に興味があるんですか?」
クラリスは小さく呟きながら、その背中をおとなしく追いかけた。
セリデン公爵が一時的に公務で忙しくしていたため、クラリスは公爵夫人の許可を得て、クノー侯爵夫人の屋敷へ向かった。
クノー侯爵家は、その名声にふさわしく、二重の城壁に囲まれた中でもひときわ大きな三階建ての邸宅を所有していた。
邸宅の中央には、女神の彫像が天に向かって手を差し伸べており、その両脇にはイチョウの木の装飾が建物を囲んでいた。
夏ならば、青々と茂る蔦に覆われた建物がとても爽やかに見えただろうが、今は冬のせいか、しっとりと垂れ下がった枯れ葉がまるで老いた動物の手のように感じられた。
かつてバレンタインが話していた『不運なクノー』という異名が、嫌でも思い出される。
まさにその時、馬車が止まった。
クラリスが扉を押し開けた瞬間、馬車の隙間から不意に手袋をはめた手が差し出された。
「びっくりした。」
驚いて見上げると、ノアが彼女の前に立っていた。
彼が今日、王都に来る予定だとは聞いていたが、まさかここまで訪ねてくるとは思っていなかった。
「ノア、どうしたの?」
嬉しさを込めて問いかけたが、彼はただ再び手を差し出すだけだ。
クラリスはとりあえず彼の手を取り、馬車から降りた。
「ここにはどうやって入ったの?」
「二重の城壁の前で、偶然サンクレア様にお会いした。」
クエンティン・サンクレアは、公爵の補佐官として長年仕えており、誰かの身分を保証するには十分な人物だった。
「そうだったのね。あとでクエンティンさんにお礼を言わないと……。でも……」
クラリスは、ノアが横に降ろした荷物に目をやった。
彼女は運搬用のカバンをそっと下ろし、中を覗いた。
「そんなにたくさん買ったの?」
「薬草です。」
「薬草……?どこか具合が悪いの?」
「痛いというより、最近心臓のあたりが少し……。まあ、大したことはありません。ご心配なく。それよりも、ここに来たのは、お嬢様にこれを渡すためです。」
彼は、青と白の花が美しく束ねられた花束を差し出した。
「お嬢様から侯爵夫人へお渡しください。」
「……ノア。」
花束には、綺麗なリボンの飾りまで付けられていた。
おそらく、ノアが慎重に選び抜いたものなのだろう。
クラリスは花束を受け取り、そっと抱えた。
「おや。」
いつの間にか馬車から降りてきたバレンタインが、興味深そうにその様子を眺めていた。
「こいつ、自分で選んだにしては、ずいぶんロマンチックな花束じゃないか?イメージが……うーん、ちょっと違うような。」
彼はクラリスの顔の下に花をかざしながら、上下に動かしてじっと観察し、顎に手を当てて考え込んだ。
「すぐに返してください!」
クラリスは彼の手から花をさっと奪い取った。
その際に、彼の手の甲を軽く叩くことも忘れなかった。
「うわっ!」
彼はまるで死にそうな声で叫びながら、手を放り出したまま固まった。
そのまま放置して、クラリスはノアの方へ向き直った。
「それにしても、どうして分かったの? 私が夫人に贈る花を悩んでいたことを。」
「さあ……。お嬢様が私の隣で『訪問の礼儀』の章を何度も読み返していたので。」
そうは言ったものの、まさか彼女のために花まで準備してくれるとは思っていなかった。
「本当にありがとう。でも、道中に花を売っている店が見当たらなくて、手ぶらで行くことになりそうだったの。」
「私が助けになれたなら、嬉しいです。」
「これ、高かった? いくらだったの?」
「そんなに高くありませんし、少女からお金は受け取っていません。ただ、私があげたかっただけです。」
「でも、申し訳ないわ。」
「そんなこと気にしなくていいですよ。今度はお嬢様が私を助けてくれれば、それでいいじゃないですか?」
ノアはどうやら友達同士でお金のやり取りをするのが苦手なようだったので、クラリスはこれ以上金額を尋ねるのをやめることにした。
「その代わり、今度ノアが何かお願いしたいことがあれば、何でも聞いてあげる。私の助けが必要だったら、必ず言ってね?」
「……何でも?」
「うん、ノアが望むことなら何でも!」
クラリスの気軽な言葉に、ノアは頬を軽く掻きながら、少し視線をそらした。
「……とりあえず、先に薬草を塗ってみますね。」
「え?」
「いいえ、何でもありません。」
ノアが突然、鞄の中から乾燥した薬草を取り出し、水に浸して飲み込もうとしたその時、玄関前の物音を察知したクノー侯爵夫人が、自ら扉を開け、彼らを迎え入れた。
突然の訪問にも関わらず、彼女はまるで驚くことなく、落ち着いた様子だった。
「本当に来てくれたのね、クラリス。」
「はい、早く夫人にお会いしたくて。」
「私もクラリスが訪ねてきてくれるのを、ずっと楽しみにしていたわ。」
玄関の階段を降りた彼女に向かって、クラリスはノアが用意してくれた花束を差し出した。
「夫人にお渡ししたくて、私の友人が準備してくれました。私はただ、それを届けるだけです。お招きいただき、ありがとうございます。」
「まあ……」
少し驚いた様子の夫人は、すぐに花束を受け取ることはせず、一瞬それをじっと見つめた。
クラリスは、もしかすると自分がとんでもない失敗をしてしまったのではないかと不安になった。
考えてみれば、娘を亡くし悲しみに暮れる夫人に花を贈ることが果たして良いことなのかと疑問に思ったのだ。
「……ごめんなさい。少し驚いて、しばらく眺めてしまいました。私のために用意してくれたのですか?」
「あ、ええ。」
何と答えるべきかわからず、戸惑うクラリスをよそに、夫人は花束を抱きしめ、その豊かな花びらの間に顔を埋めた。
「花を贈られるのは久しぶりですね。」
その香りを堪能する夫人は、心から幸せそうな微笑みを浮かべていた。
「ありがとう。本当に嬉しいです。この香り……懐かしいわ。」
「気に入っていただけてよかったです。」
「昔は、セシリアが庭の花を摘んでよくプレゼントしてくれたものです。もちろん、花びらを無理やりちぎったせいで、しおれかけたものばかりでしたが……。それでも、あの子はその贈り物をとても大切にしていました。」
彼女は、再び花の香りに包まれながら、穏やかにその思い出に浸っていた。
「まるで時間が戻ったみたい……。」
しばらく花を楽しんでいた夫人は、ふと我に返ったように驚き、少し困惑したような笑みを浮かべた。
「申し訳ないわ。あまりにも嬉しくて……。それにしても、こんなに立派な紳士方と一緒に来てくださるなんて。もしかして、お二人ともクラリスに求婚しにいらしたの?」
求婚?
クラリスはもちろん、ノアもバレンタインも驚愕し、夫人の発言を慌てて否定しようとした。
「まさか、そんな……久しぶりですね。最近でも、こうしてご夫人の知恵を仰ぎに来る立派な青年がいるとは思いませんでしたよ。懐かしいですね……。」
クラリスは慎重にバレンタインを見つめた。
彼はこの国の王子であり、礼儀作法についてどこまで理解しているのかは分からない。
しかし、彼は完全に何も分かっていないような表情を浮かべ、呆然としていた。
もしかしてと思いノアも振り返ってみたが、やはり彼もただ硬直しているだけだった。
「あの頃はとても楽しかったですよ。若いお嬢様が求婚者を連れてくると、貴婦人たちはそれぞれの秘策を使って、誰が一番良い男性なのかを見極めようとしたものです。」
そんな風習があったとは。
クラリスは驚きながらも、少女のように楽しそうに語る夫人の表情が心なしか嬉しく思え、微笑みながら問いかけた。
「侯爵夫人も良い求婚者を見極める秘訣をお持ちなのですか?」
「もちろんよ。たった三つの質問をすればいいのです。実は……。」
彼女は花束をしっかり抱えながら、ふと寂しげな表情を浮かべた。
「いつか……私の娘が求婚者を連れてきたら、この質問をしてみようかと考えていました。それだけのことなのに……なんだか、悲しいわね。」
「そんなことはありません。」
クラリスは、あまりにも切なく胸が締め付けられる思いだった。
握りしめた手に、自然と力がこもる。
亡き娘を思いながら、求婚者たちに投げかけるはずだった質問を考え続けていた夫人が、どれほど心を痛めていたことか。
「でも、こうして機会が訪れたのを見ると、ひとりで質問を考えていた時間も、決して無駄ではなかったようですね。」
「……え?」
「はっ、こんな時じゃないわね。いつまでもお客様を立たせてしまって、ごめんなさい。」
誤解を解く間もなく、彼女は三人を応接室へと案内し始めた。
歳月を感じさせる邸宅は、内部もまたその風格を失ってはいなかった。
装飾も絵画もない廊下を抜けると、磨かれた床が続いていた。
足音を響かせるたびに、かすかにきしむ音がした。
クラリスは、夫人がこの床を意図的に一部修理していないことを確信した。
それは、応接室へ続く壁の一角に、小さな子どもが身長を測った跡が残されていたからだ。
壁に引かれた複数の線のそばには、「CC」という文字と日付が記されていた。
亡くなった娘の名前がセシリアだと聞いていた。
セシリア・クノー、つまり「CC」。
そして、もうひとつ、「マックス」と書かれた名前もあった。
その線は比較的高い位置にあったため、CCよりも数歳年上の子どもだったのだろう。
つまり、この床は……
セシリアが駆け回り、友人と一緒に身長を測った場所だったのだ。
夫人は、この古びた床のどこかに、セシリアの小さな痕跡が残っているかもしれないと思い、あえて修理しなかったのかもしれない。