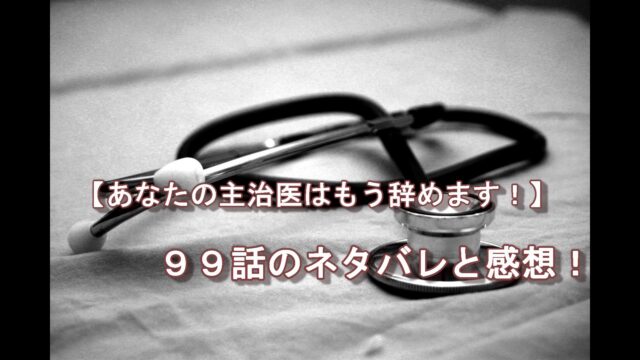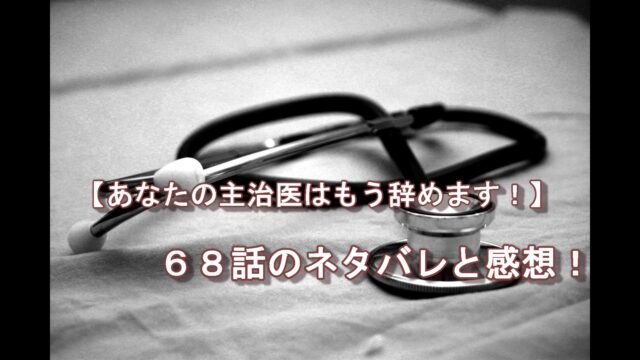こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

160話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- IF リチェがモレキン家に養子として入ったなら②
その後、ディエルとリチェはかなり親しくなった。
セレイアス公爵邸で一緒に過ごしたからだ。
そして半年後。
二人は「父母の日」を迎え、久しぶりにモレキン邸へ一緒に向かっていた。
道中、二人はずっとアルガのことを考えていた。
アルガが行方不明になった娘をどれほど想っているか、身近で見てきた彼らが一番よく知っていたからだ。
「よりによって『父母の日』とは……」
ディエルが気まずそうに呟くと、リチェは喉を鳴らしたあと、深いため息をついた。
「まあ、どうせ私たちがしてあげられることなんてないんだから。それに……エルアン公子だって、公爵夫人に手紙なんて書かないでしょう?だから特に失礼だなんて思われないはずよ。」
エルアンとイサベルの仲は良くなかった。
侍女たちの話によると、エルアンはもう十六歳になるが、一度もイサベルに「父母の日」の手紙を書いたことはないらしい。
「まあ、そうでしょうね。むしろ君に手紙を書いていたら別かもしれないけど。」
ディエルは静かにそう認めた。
実際、エルアンはリチェにかなり親しかった。
いとこのウェデリックよりも最近はもっと親しく過ごしていたのだ。
リチェにとってもエルアンは実際、彼女が診た最初の患者でもあったため、彼を看病するのに最善を尽くしていたから。
「君が来てから、公子様が私にもとても親切になったよ。いつも冷たくて近寄りがたい方だと思っていたのに。」
ディエルはにやりと笑いながら背もたれに体を預けた。
「俺が君の兄だから、仲良くしていたいんだろう。」
「それはいいことね。正直に言えば、私は公子様と兄さんの関係にはあまり興味ないけれど。」
「なぜ。」
ディエルが細めた目でじっと彼女を見つめた。
「公子様って、なんとなく怖そうに見えるよね……。護衛兵でもないのに、睨まれたら背筋がゾクッとしそう。」
「まあ、元気で暮らしてるなら良かったけど。」
リチェは興味なさそうに肩をすくめ、話題を変えた。
「それで、お兄ちゃんは手紙書いたの?久しぶりにお母様に会うんだし。」
「書いてないよ。俺はもう十六だ。そんなの子供がやることだろ。」
ディエルはそう言いながら、無造作にリチェの髪を撫でた。
「じゃあ、君は書いたの?」
「そんなの子供がやることだってば。」
リチェも同じように、何気なく受け流した。
「保育院では十三を過ぎれば独立するんだ。」
リチェは書類上ではモレキン夫妻の娘だった。
そしてディエルに従って「父母の日」にモレキン邸に一緒に来たのも事実だった。
しかし不思議なことに「父母の日」の手紙を書くことはできなかった。
実際にペンを取ってはみたものの、本当に書く言葉がなかったのだ。
『これは私が出来の悪い子だからじゃない。』
それ以上問わないディエルを見ながら、リチェはひとり静かに考えた。
『ただ……親子の情を感じるには一緒に過ごした時間があまりにも短かったから……。』
実際、数か月も一緒に過ごしていないのに手紙を書くのは少し気恥ずかしかった。
それでも公爵邸で受け取った給料で大きな花かごを持っていくところだった。
『実際、一緒に過ごした時間はセレイオス城の人たちの方がずっと長いよね。』
リチェは、毎日自分を気にかけてくれる人たちのことを思い出した。
ちょっとでも気に入ったものがあれば、彼女に内緒でワンピースやお菓子を送ってくれるイサベル。
いつも手をぎゅっと握りしめて、彼女が言うとおりに真剣に体を鍛えようと頑張っているエルアン。
そして……いつもぶっきらぼうだけど、『お前を捨てたりなんかしない、分かった?』と口にしながら、何かと世話を焼いてくれるアルガ。
「ねえ、お兄ちゃん。」
リチェはそっとディエルを呼んだ。
「今日は泊まっていくのでしょう?」
「うん、休暇は明日までだから。」
ディエルは素っ気なく答えた後、しばらく目を瞬かせて何かを察し、にやりと笑った。
「でも、お前は今夜、公爵邸に戻るのもいいかもしれない。夜にエルアン公子が訪ねてくるかもしれないし……。」
わざとエルアンを引き合いに出したが、心の奥ではディエルはリチェがどこをより心地よく感じているのかすでに理解しており、それを確認しただけだった。
「両親は寂しがるだろうけど、それでもお前は養子に迎えられた身だから仕方ないじゃないか。」
リチェは少し気まずそうに笑った。
そして静かに「ありがとう、お兄ちゃん」と心の中でつぶやいた。
ディエルはなぜかひどくこそばゆそうな表情を浮かべてみせた。
ある夜、セレイオス公爵城。
遅くまで明かりが灯っている部屋があった。
そこはセレイオスの小公子、エルアンの部屋だった。
「うーん……だから、エリベリズムの意味は……」
エルアンは久しぶりに本を読みながら勉強していた。
本来なら頭痛がするから勉強なんてするなとウェデリクに言われて、本から遠ざかっていなければならなかった。
だが、そのすべてはアルガの弟子であるリチェが来てから少しずつ変わっていったのだ。
最初、エルアンはリチェに特に関心を示さなかった。
むしろ他の助手たちより年下で、少し戸惑っていたのも事実だった。
「そんなに一生懸命やる必要はないよ。どうせ痛いとも思わないだろうし。」
しかし、自分の様子を確認しに来たリチェにぶっきらぼうにそう言ったとき、リチェは淡々とした表情で答えた。
「一生懸命やっていれば分かるかもしれません。私は天才ですから。12歳で助手にスカウトされたのを見れば分かるでしょう?」
もともとそれほど謙虚な性格ではなかったが、アルガが直接「弟子にしてほしい」と頼んだということで、リチェはとても堂々としていた。
「それでも公爵家の十三歳でしょ。患者を診た経験があるわけじゃないんだから、大したことはないさ。」
「じゃあ、公子様は私の初めての患者というわけですね!いつかそれが公子様にとって大きな誇りになるよう、私もこれからしっかり生きていかないといけませんね。公子様も絶対に回復してください。」
リチェのその自信に満ちた言葉を聞いていると、本当に彼女と一緒に成長していくうちに、自分の病も治っていくような気がした。
だからいつしかエルアンは、徐々にリチェに心を許し始めていた。
ウェデリクが訪れたある日、同じ席にいたリチェはすぐにエ르アンに、ウェデリックの言葉を聞かないよう忠告した。
まったくもって的外れな話で、ただ寂しがり屋の自分を構ってほしかっただけなのだ。
「エルアン様、私の初めての印象を台無しにするおつもりですか?まずは私を信じてください!」
どこか立場が逆転したように見えたが、それでもリチェは決して間違ったことは言わなかった。
それにウェデリックはたまにしか来なかったが……リチェは常に同じ階の近くの部屋にいたのだから。
「私と一緒にうまくやってみましょう。ね?今、私は使命感に燃えているんです。最初の患者は一生忘れられないって言うじゃないですか!」
リチェの言葉を聞いていると、聞けば聞くほど少しずつ強くなっていくような気がした……。
それでエルアンはリチェの言う通りに、食事もきちんと摂り、運動も一生懸命にして、本もよく読むようにした。
『初めての患者は一生忘れられないというから……。最善を尽くす姿を見せなければ、自分も誇らしいはずだ。』
エルアンにとって、誰かが自分にそんな意味を与えてくれるのは初めてのことだった。
前よりずっと良くなったと笑っているリチェの姿を見ると、胸がいっぱいになった。
だから今朝、リチェが養父母に会いにモレキン邸へ行くと言ったとき、少し寂しくも感じたのだった。
しかし、明日には戻ってくるというのだから……。
いくら「両親の日」とはいえ、イサベルの顔を見ることはできなかった。
今日は領地内で何やら裁判があるとかで、夜明け前から出かけてしまったのだ。
それでもイサベルよりリチェの不在のほうがずっと大きく感じられた。
リチェのいない屋敷はただ虚ろに思えた。
「これはウェデリック兄さんが毎日僕にくれるお菓子なんだ。一緒に馬車に乗って行きながら食べようか?これを食べればお腹も痛くならないし、頭も痛くならないんだよ。」
「え?そんなお菓子、この世に存在しませんよ。一度見せてください。」
特に、初めてセレイオス城を離れるリチェに、大きな決心をして贈り物を渡したのに、リチェの反応が思ったほど強くなくて、余計に気になった。
「帰ってきたら、明日私が詳しく見てみますね。」
ウェデリクが「とても高価で貴重なものだから、誰にでも渡してはいけない」と念を押していた菓子だったのに……。
そんなに反応が薄いのなら、いっそ返してほしいと思ったくらいだ。
「これのせいでも、予定より早く戻ってきてもらわないといけませんね。」
エルアンは口を閉ざしたまま笑みを浮かべ、リチェを見つめた。
少しでも早くリチェに会えるのなら、その菓子には十分な価値があると感じていたのだ。
「リチェ……」
エルアンは本を読みながら静かに呟いた。
「早く来て……」
ウェデリックでさえ、これほど切実に待ち焦がれたことはなかっただろう。
いつの間にか、その小さな助手が彼の心の中に大きな居場所を占めていたのだ。
一方、その頃アルガもまた眠れずにいた。
彼はリチェの部屋のテーブルに静かに座っていた。
こぢんまりとした雰囲気のその部屋は、実は行方不明になった彼の娘のためにイザベルが公爵邸の中で用意してくれたものだった。
偶然見つけた有能な助手に、いつも空いていた部屋を与えただけだったが。
実のところ「両親の日」そのものは、彼にとってもう悲しみではなかった。
子どもたちから手紙を受け取る親を羨む余裕すらなかったのだ。
彼には、一日でも早く娘を見つけたいという焦りだけが募っていたのだから。
きちんと整理された部屋を見渡しながら、アルガはひとり小さく笑った。
「……あの子が公爵城を留守にするのは初めてか。」
ちょこまか動き回っていたあの少女が、今はモレキン邸へ行っているからだろうか。
今日はやけに公爵城が静かに感じられた。
体調がすぐれなかったものの、エルアンも部屋に閉じこもったまま出てこず、イザベルもティータイムに誰も呼ばず静かに過ごしていた。
そして彼自身もまた……。
『いつもと同じ部屋なのに、今日はなぜか広く感じるな。』
その時だった。
突然、ドアが勢いよく開いた。
「えっ……侯爵様?」
考えもなく自分の部屋に入ってきてしまい、驚いたリチェが目を大きく見開いた。
アルガもまた驚いて尋ねた。
「おまえ、今日はディエルと一緒にモレキン邸に泊まってくるって言ってなかったか?」
「はい、夕食だけご一緒して、私は帰ってきました。」
リチェはにこりと笑って肩をすくめた。
それでもリチェは「なぜ私の部屋にいらっしゃるんですか?」とは言わなかった。
この部屋の本来の持ち主が誰なのか、すでに知っていたからだ。
「なぜ?」
「ただ……ここがもっと楽で、心地いいからです。」
「まあ、そうだな。」
モレキン邸がどんなに立派だとしても、所詮は平民の家。 公爵邸より優れているはずがなかった。
アルガは無言のまま立ち上がった。
「それなら、心地よい部屋で存分に休むといい。まあ、明日の朝食は一緒にとろう。ただ、特別楽しみにしているわけじゃないぞ。」
「はい。あ、それから……」
ひょいと歩き出し、もう部屋を出ようとするアルガの服の裾を、リチェが慌ててつかんだ。
そして短い手紙が入った小さな封筒を差し出した。
アルガの目が大きく見開かれる。
「これは何だ?まさか『両親の日』の手紙とかじゃないだろうな?」
「違いますよ!そんなの、もっと子どもの頃だって書いたことありません。私、子どもでもないし……。」
リチェがぶんぶん首を振って否定した。
「ええと、ただの落書き……みたいなものです。」
「そうか?じゃあその落書きとやら、見せてもらおうか。」
アルガはその場で封筒を破り、手紙を確認した。
<公爵さま、元気を出してください。私が親子剣士の研究を続けます。もちろん私は一人でも十分生きていけるので、両親を探そうなんて思ったことはありませんが……公爵さまの心があたたかいから、公爵さまのために一生懸命やろうと思ったんです。>
手紙を読んだアルガはしばらく黙って立っていたが、ふっと笑みを浮かべ、リチェの頭を撫でた。
「親子剣士の研究……ありがたい。サンプルが必要になったら、いつでも私のを持って行って使え。」
「はい、そうします。」
「ともあれ『両親の日』に手紙をもらうとはな……私がその大半を務めることになりそうだな。」
「落書きですよ。」
リチェは気まずそうに、とりあえず必死に笑ったあと、すぐに話題をそらした。
「それに……ちょっと気になることがあって来たんです。今日中にこの落書きを渡そうと思って来たわけじゃなくて。」
「気になること?」
アルガがそう言うと、リチェは上着の中からビニール袋に入った小さな封筒を取り出した。 保存袋の中に入っていたのは普通のお菓子だった。
「これ、ウェデリック様がよくエルアン様にくださるお菓子だそうです。頭も痛くならないし、お腹も壊さない、奇跡の食品なんですって。ご存じでしたか?」
アルガは厳しい顔つきで外縁メガネをかけ直した。
そして、困惑したように黙り込んだ。
「……食べているものを細かく記録しろと言われたんだけど……」
「私が簡単に分析してみたんですが、時間がなくて……そのせいか、組み合わせがちょっとおかしいんです。 一度見ていただけますか?」
「そうか。じゃあ、これは私が預かろう。」
挑戦すべきことができたアルガは、すぐに封筒を受け取り、挨拶もせずに出て行ってしまった。
・
・
・
翌日、リチェのその手紙はアルガの研究室の机の中央に貼られていた。
そして朝から上機嫌な顔で、イザベルに向かってこう冗談めかして言った。
「奥様は『両親の日』に、こんなもの受け取ったことないでしょう?」
その時も、問いただす暇もなく忙しく駆け回っていた。
しかしイサベルには、その言葉に心を痛めている余裕すらなかった。
数時間後、ウェデリックが渡したという菓子の分析を終えたアルガが、公爵邸をひっくり返すように動いたのだ。
まずエルアンは治療のためにすぐさまイルビアへ向かった。
そしてイサベルはその事件を追及する中で、自分もまた陰謀に巻き込まれていたことを知り、反乱軍を突き止めることができた。
自分の不注意によってエルアンの健康を害してしまったという罪悪感に、イサベルはひそかに涙を流した。
だがジェイドの無事を知った後には「息子はあの子だけでも助かって本当に良かった」という思いで、ようやく心を落ち着けることができた。
「そうね……リチェのおかげで頭があんなに悪化せずに済んだのは、不幸中の幸いだわ。」
イザベルはリチェを抱き寄せて言った。
「ずっとセレイオス城に残ってくれる?あなたを手放したくないの。」
リチェは素直にうなずいた。
しかしエルアンもおらず、その後これといった用事もなくなったリチェは、約束を守るために熱心に親子鑑定の研究に没頭した。
実験用サンプルとしてアルガの髪の毛と自分の髪の毛を使い、それが親子であることを知ることになったのは、それから1年後のこと。
そのとき、アルガはほとんど気を失いそうなほどの幸福を感じた。
毎日、自分に起こった奇跡に感謝し、娘と共に楽しい時間を過ごしたのだ。
「これ以上、悲しいことは私には起こらないだろう」と、口癖のように繰り返しながら。
しかしその言葉がむなしく、5年後のアルガは思わず寂しさに沈んでしまった。
治療を終えてイルビアから戻ったエルアンとリチェが、純粋な恋愛を始めてしまったからだ。