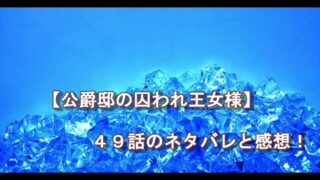こんにちは、ちゃむです。
「できるメイド様」を紹介させていただきます。
今回は184話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

184話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 王室騎士団④
一方、マリはクローヤン地方の北、ハワード侯爵の領地に向かっていた。
まさにハワード侯爵にできた重病を治療するために。
「よろしいのですか?一見しても危険な手術だと思うのですが」
ポンティル男爵は心配そうな口調で尋ねる。
「閣下は善意で出るのですが、結果が良くない時に悪い意図を持ったものが悪い噂を広めるのではないかと心配です」
マリも男爵の心配に同意した。
ハワード侯爵。
かつてクローヤン王家に仕えていた大貴族で、王国民から根強い尊敬を受けている。
帝国が王国を占領した後は抵抗の意志で領地に蟄居中だった。
王室騎士団団長であるバルハン伯爵の師匠でもあるので、彼を生き返らせることができれば、国民の心をつかむのに大いに役立つだろう。
だが、成功時に得られる利盆が大きいということは、失敗時に甘受しなければならない危険も大きいという意味だった。
(下手をするとハワード侯爵が死んだと噂になるかもしれない。いや、きっとそういう風に噂になる)
問題は、この手術が成功よりは失敗する確率がはるかに高いということだ。
マリはしばらく悩んだ末に決めた。
「ただ無駄なことは考えないようにします」
「え、それは一体?」
ポンティル男爵は怪謗な顔をした。
「いろいろな政治的事項を離れて、ハワード侯爵は死の危機に瀕した患者なので、それだけを考えるつもりです」
そう、それがマリの結論だ。
しばらく政治的損益を予想していた彼女は、一瞬これではないという気がした。
最初、彼女が能力を望んだのは、他人を助けることができる人生を生きたかったからだ。
今、助けが必要な人がいて、彼女には助けられる能力がある。
マリはそれだけ考えることにした。
「なるほど」
ポンティル男爵は結果が心配だったが、彼女らしい結論だと思った。
「到着したんですね」
マリは馬車から窓の外を眺める。
山の下に小さな古城が見えた。
ハワード侯爵の領地だった。
「総督閣下にお目にかかります!」
マリが侯爵の城に到着すると、多くの人が集まって挨拶をする。
ハワード侯爵の重病の知らせに臨終を守るために駆けつけたクローヤン地方の貴族たちだった。
(すごく多いんだね)
マリは驚いた目で視線をそらした。
彼女に挨拶しに来た王国の貴族だけが数十年前のように見えた。
それも一つ一つが名高い貴族だ。
(侯爵が王国貴族の精神的求心点だとは)
帝国に占領されたからといって、王国の貴族がすべて入れ替えられるわけではない。
帝国に忠誠を誓えば普通以前の領地を認めてくれたが、実はハワード侯爵はそのまま領地を認めるには危険性が高い人物だったが、王国民の尊敬があまりにも深くて触れることができなかった場合だった。
「ところで閣下、ここには何のご用ですか?」
貴族たちがマリに尋ねる。
そんな彼らの瞳にはさまざまな感情が入り混じっていた。
疑惑、警戒心、帝国の総督であるマリヘの敵対感など。
とにかく好意的な感情は見当たらなかった。
(あの中で密かに王室の騎士団に紐をつけている人もいるだろう)
そんな考えをすると、心の中の負担感が大きくなる。
しかし、マリは心の中で首を横に振って言った。
「ハワード侯爵に会いに来ました」
「そうなんですか?ご案内いたします」
マリはポンティル男爵と一緒に城に入る。
侯爵の城は質素な人柄がそのまま反映され、索漠としたほど装飾がなかった。
マリは廊下を歩いて部屋の奥深くに着いた。
「こちらです。侯爵閣下は病状が重く、意識がありません。現在、養子がそばを守っています」
うなずいたマリは部屋に入ってびっくりする。
「・・・」
横になっている老年の男のそばに思いもよらない人物がいたのだ。
王室騎士団団長のバルハン伯爵と王室騎士団の騎士だった。
「王室騎士団!」
ポンティル男爵はバルハン伯爵に気づいて驚き、剣を取り出す。
思いもよらない場所で敵に会ったのだ。
王室騎士団の騎士たちも剣を取り出した。
病室があっという間に荒々しい殺気に覆われる。
今にも血が飛び散ろうとする危機の瞬間!
「ちょっと待って!ここは病室です。止めてください!」
「止まれ!」
マリだった。
ところが意外な声がもう一つあった。
バルハン伯爵が固い顔で騎士たちを引き止めたのだ。
「団長?どうして?」
騎士たちは不思議そうな表情でバルハン伯爵を見る。
ポンティル男爵も同様だった。
彼らは常にマリを暗殺しようとしていた王室の騎士団だ。
絶好のチャンスに出会ったはずなのに引き止めるなんて?
「・・・」
しかし、バルハン伯爵は何の返事もなく、重い目でマリを眺めるだけだった。
彼の剛直な顔に混乱、苦しみ、恨みなどの感情が入り混じって通り過ぎる。
その場でマリだけがバルハンの気持ちを理解した。
モリナ王女であり、帝国の予備皇后である自分にどう接するべきか、苦しくて混乱しているのだろう。
その時、騎士の1人が声を上げた。
「団長、今すぐあの女の首を叩かなければなりません!」
ところが、その言葉を聞いたバルハンがかっと声を高めた。
「黙れ!あの女だって?貴様が死にたいのか!」
そう叫んだ彼はびくっと立ち止まった。
モリナ王女に暴言を吐くのを見て、反射的に怒ったのだ。
バルハンは呆然とした表情の部下に言い聞かせるように言った。
「あ・・・あまりひどい言葉はよくない。我々は誇らしい王室の騎士団だ。品位を守れ」
「・・・はい」
「とにかく一度退出してくれ。父の臨終が迫っているのに、騒がせたくない」
王室の騎士団は首をかしげて身を引く。
マリもポンティル男爵を送り出した。
二人きりで残ることになると、バルハン伯爵がマリに向かってひざまずいた。
「王室騎士団のバルハンが偉大な王家の末裔、モリナ王女殿下にお会いします」
王族に向けた儀礼。
バルハンは彼女をモリナ王女と認めたのだ。
しかし、認めたからといって目つきの混乱が落ち着いたわけではない。
当然だった。
すべてを捧げて彼女を待っていたのに、帝国の予備皇后になって帰ってくるとは。
しかも彼女は王家の再建を望んでもいない。
彼の立場からしてこんな天の露震もないだろう。
マリは彼の視線に込められた混乱と恨みを見つめながらため息をついた。
「お立ちなさい、伯爵」
「はい、殿下」
「伯爵はハワード侯爵の養子ですか?」
「そうですね。侯爵閣下のお子さんがいなくて私が臨終を守っていました」
バハルンの話し方は非常に丁寧だったが、マリは自分のことを自分の気持ちとして認めていないということを感じることができた。
「私は王女殿下の意思を受け入れることができません」
マリはうなずいた。
「ええ、そうだと思います」
バルハンの目に疑惑が宿る。
彼は彼女が自分を説得しようとするだろうと予想していたのだ。
「今日は伯爵に用があるわけではありませんから」
「では、ここにはどうして?」
「申し上げたとおり、ハワード侯爵に会いに来たのです」
彼女の言葉にバルハンの目に悲しみが宿った。
「お父様のことですか?そうなんですね」
バルハンは意識を失っているハワード侯爵を見た。
マリの侯爵に対するバルハンの気持ちはつらい目によって感じられた。
バルハンはハワード侯爵を口先だけの養父ではなく、本当に実の父親と変わらない存在だと思っていることが明らかだ。
「お父さん。お父さんが待ちわびていたモリナ王女殿下がいらっしゃいました」
バルハンはハワード侯爵の手をぎゅっと握る。
しかし、どんな剌激を与えても侯爵は微動だにしなかった。
バルハンはこみ上げてくる悲しみをこらえるために唇をかんだ。
「すみません、殿下。心の準備をしていましたが、受け入れるのが簡単ではないですね。実の父と変わらない方なので」
「・・・」
「こんな風に亡くなる方じゃないのに。クローヤンためにしなければならないことが多いすですが。急にこんな病気にかかって」
バルハンは嘆かわしいように言った。
その時、じっと聞いていたマリが口を開く。
「伯爵、一つだけお尋ねします。もし侯爵の病気を治す方法があれば、試してみますか?」
バルハンは苦々しく首を横に振る。
「残念ながら、そんな方法はありません。すべての医師が手を休めて久しいです。ヒポクラテスが戻ってきても父を生かすことは・・・」
そこまで話した時だった。
バルハンは口をつぐんだ。
クローヤン地方の首都、コモン城で飛び交う彼女に対する噂の一つを思い出したのだ。
彼女が不可解な境地の医術を持っているという噂を。
「まさか・・・殿下の御出で?」
マリはそっとうなずいた。
「はい、私は侯爵を治療するために来ました」
彼女は固い意志のこもった声で話した。
「もちろん、私がやろうとしているのは極めて危険な手術です。しかし、私は危険を冒してでも侯爵を治したいのです」
「・・・」
バルハンの目つきが揺れる。
マリは彼の瞳をじっと見つめながら尋ねた。
「私を信じて、父の手術を任せていただけませんか?」
思いがけない場所でバハルンと遭遇。
彼は手術をマリに任せてくれるのでしょうか?