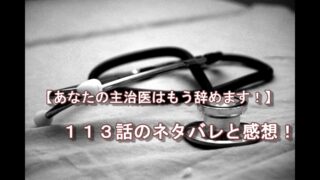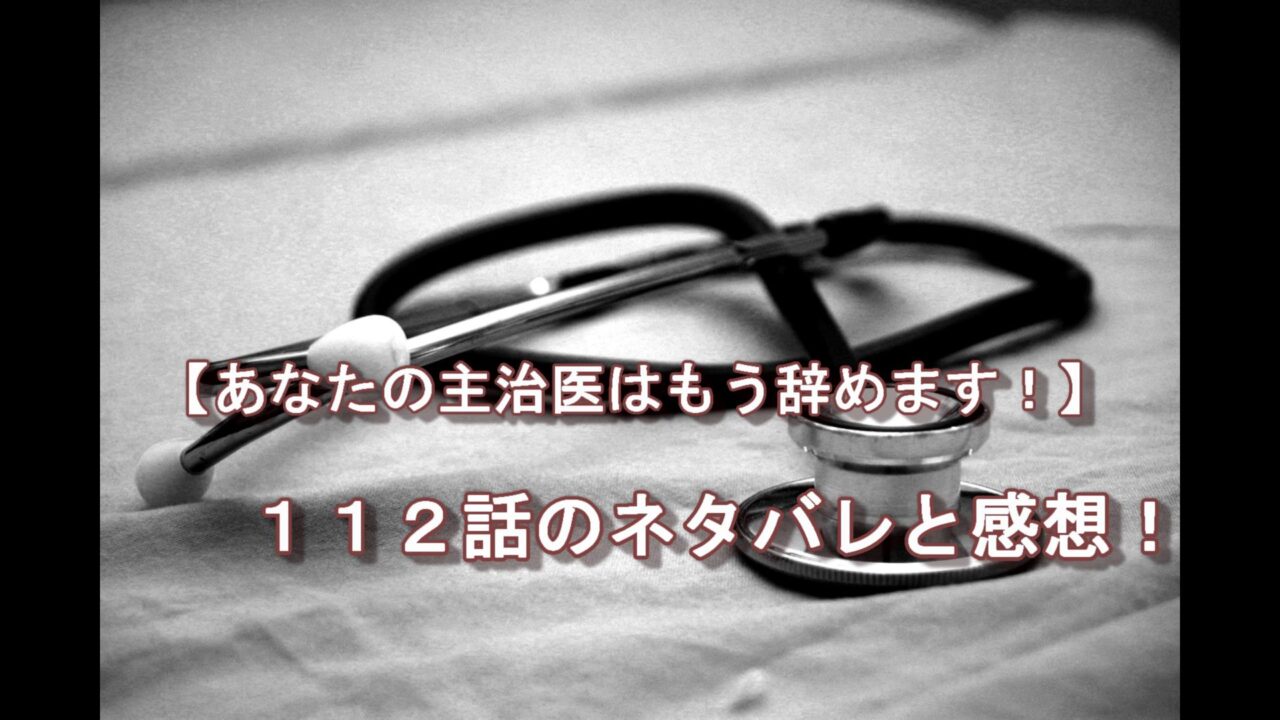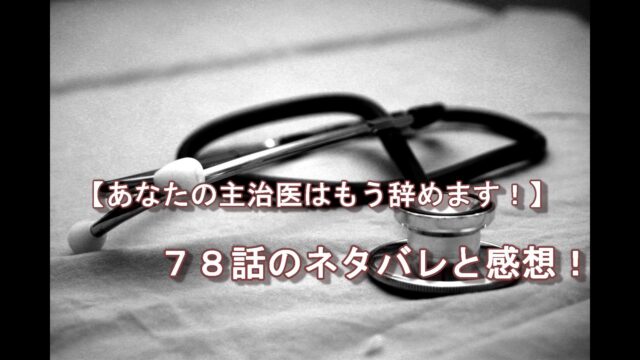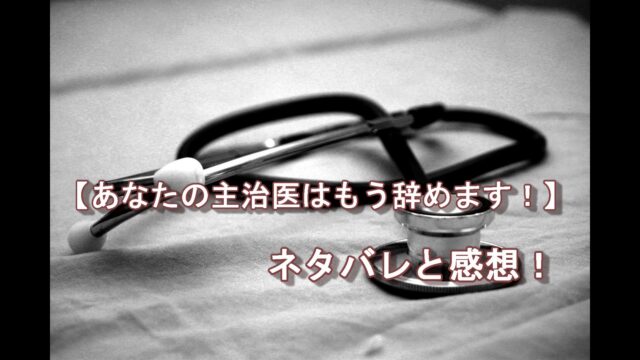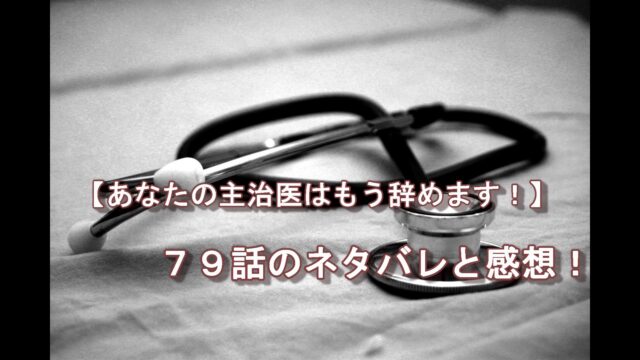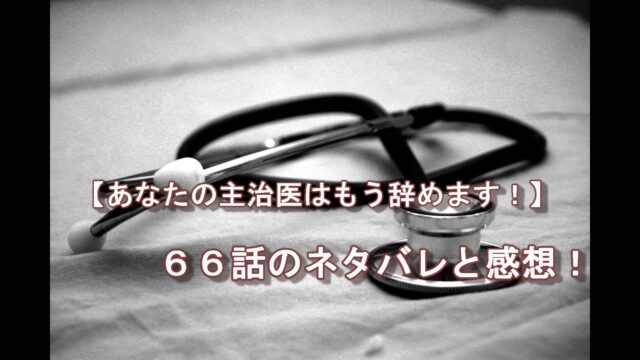こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
今回は112話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

112話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 戸惑い②
「フェレルマン侯爵がどうすべきかわからないのなら、正直に話してみたらどう?」
「いいえ。」
私はそっと頭を横に振った。
「ただ・・・話を持ち出すのもちょっとためらわれます。会話をしているうちに、本当にそう思っていることに気づかれたら、相手を傷つけてしまうと思うんです。」
「そんなこと言わないで、君のせいじゃないよ。もし僕がハエルドン皇帝のように邪魔になる人間をすべて殺していたら、とっくに帝国の未来は尽きていただろう。」
エルアンは私を慎重に抱きしめながら言った。
「間違いがあるとすれば、それは当然その卑劣な男のせいだ。そしてもう一つは、神を冒涜した罪のせいだ。いや、それにしても『神を冒涜する』なんて表現はそんなに悪い言葉だったかな? あの家ではそう言っていたのかな?」
彼はそっと私の背中を叩いてくれた。
「そのくだらない家の言葉は確かに合ってるよ。神の加護なんてものをありがたがって食べろと言われても、どうしても嫌だと感じる。信仰を踏みつけにしてやりたい気分だよ。全く、あんな信託が下りてきて・・・。」
「まあ、そういうこともあるでしょうね。でも、もし本当に最初から神が私を駒にして不幸を計画していたのなら・・・私が公爵様の愛人としているのも少し変な感じがします。」
「・・・え?」
「それより、早く離れてください。」
私は彼を軽く押しのけながら言った。
「私はもう全身ずぶ濡れなんですよ。公爵様も濡れてしまったでしょう。暖かい南部で健康を回復した身体だから、少し寒くなると公爵様の体に悪影響が出るかもしれませんよ。ちょうど季節の変わり目ですし。」
「それが。」
彼は低く笑った。
「もう濡れているし、傘を差しても変わらないかもしれないね。」
そう言って、私が何か言う間もなく、手にしていた傘をぽんと地面に置いた。
「公爵様?」
先ほどより強くなった雨のせいで、その傘もすぐにびしょ濡れになる。
「こんな表情を作った神を殺してやりたいくらいだ。」
そう言いながら、彼は私を再び抱きしめた。
エルアンはいつもこんな調子だった。
何か理由を挙げて拒否すると、その理由が通用しないようにして、結局受け入れざるを得ない状況に追い込んでくる。
「君のお母さんを再び生き返らせることもできないなんて、つらい話だ。」
それに対して何も言い返せずにいると、彼が私の額にそっと唇を寄せてきた。
「僕は全知全能じゃないから、傘で君が雨に濡れるのを防ぐことができないなら、一緒に雨に濡れることくらいはできる。」
その言葉に、私は目を上げてエルアンを見た。
身長差が随分とあったため、抱かれたままでは彼の目を見ることはできなかったが、私に向けられた温かな視線だけは感じ取ることができた。
「僕が何を言っても、君がそんな考えを抱くのを止められないだろうけど・・・。とにかく、同じ姿で君のそばにいるから。」
私が初めて人生の荒波の中で、まだ幼い子供の姿を見つけたとき、こんなふうに温かく抱きしめて、こんなに大きな慰めを与えてくれる人が現れるなんて、少しも思っていなかった。
「そんなふうに考えなくてもいいけれど、たとえ君が本当に不幸の原因だとしても、喜んで君と同じ不幸を分かち合うよ。」
「公爵様、とりあえず中に入りましょう。まだ外は気温が低いですし、このままだと何か体調に影響が出るかもしれません・・・。」
「辛くてもいい。君が一人で雨に濡れるよりも、それで少しでも君が良くなるなら僕は構わない。」
そう言いながら、彼は私の手を引き、公爵邸の中へと連れて行った。
たぶん私がこれ以上雨に濡れるのを見たくなくて、ここまで計算して彼自身も傘を投げ捨てたのかもしれない。
「どれだけ不幸でもいい。君がいないよりは。僕には君がいればそれだけで幸せなんだ。」
その言葉に、私は彼のそばにいることを確信し、心が温かく満たされた。
彼の言葉に何も返せず、ただ彼と一緒に城内へと戻る。
一人でいると、抑えきれなかった思いが再び胸の中を掻き乱し、悪い考えが頭をもたげてくるような気分だった。
「落ち込むのはやめて、明日、宮廷の調査団が到着したらハエルドン皇帝とイシドール男爵にどうやってきっちりと報いを受けさせるか考えよう。」
「えっと・・・はい・・・」
「残酷で悪いことは嫌い?」
階段を上っていたエルアンがどこか楽しそうに微笑みながら言った。
「大丈夫、僕が本当に上手くやるから。何も考えず僕に任せて。」
彼なら本当に上手くやってくれるという確信があった。
研究室で一度見たウェデリックの抑えきれないほどの執念深さを思い出し、思わず目を閉じる。
エルアンが優しく話題を変えた。
「フェレルマン公爵が戻ってきたら、君の正直な気持ちを話してみなよ。僕が見る限り、フェレルマン公爵は君の目を見つめるだけで気持ちが良くなるどころか、逆に嫌でも仕方ないみたいだから。」
「本当に喜んでくれるでしょうか?」
「とりあえず言ってみなよ。君が公爵の娘じゃなかった頃から、フェレルマン公爵は君をとても大切にしていたじゃないか。」
「・・・はい。」
私は小さく微笑んだ。
「そうします。」
「やっと笑ったね。」
エルアンがほっとしたように言った。
「知ってる?」
「え?」
「君が笑うと世界が止まったみたいに感じるよ。」
彼は優しく笑いながら、私の濡れた髪の毛をそっと絞ってくれた。
「12歳の頃、君が一緒に遊ぼうと言っていた時から、ずっとそんな気がしていた。」
昔の思い出が蘇り、私もまた彼と同じように笑みを浮かべていた。
かつての感情がよみがえり、ついくすくす笑ってしまった。
「どんな神様だって、君を苦しめることなんてできないさ。リチェ、君は僕にとっての救いだよ。」
作り話のように心を惹きつけてくるその言葉通り、エルアンは私を慰めようと決心したようだ。
「そしてリチェ、君を知る人なら誰でも、同じように思うはずだよ。」
その夜、エレナンは私が眠りにつくまで、枕元で見守り続けてくれた。
「だから逃げないで、リチェ。」
「・・・。」
「君は、内面から光を放つ人間だ。だからきっと良い結果になると信じてる。でも、もし悪い結果になったとしても、僕は絶対に君のそばにいるから。」
大きく変わった見た目と同じくらい、内面にも深い傷を負っている自分を感じていた。
それでも、そんな私を支えてくれる彼の存在が頼もしかった。
その夜、彼がこんなにも自分を守ってくれる存在になったことに、私はただ驚くばかりだった。
「僕も約束するよ。絶対に健康を取り戻して、どんなことからでも君を守るよ。」
ずっと昔、幼いエルアンが私にしてくれた約束のように、彼は私をすべての悪い考えから守ってくれている気がした。
眠りが浅くなるたびに、不安げな瞳で私の手を握りしめている彼を見て、私は心が動かされるような気がした。
彼はただ私に優しさを注ぎ、時折からかうだけではなく、私が弱っている時には心から寄り添い、共に雨に打たれても平気でいてくれるような恋人だった。
エルアンがここまで格好良くなくても、結局は好きになったんだろうなと思う。
それは私にとって本当に驚くべきことだ。
無条件の愛を受けるということは、傷つくことへの恐れが和らぐことだと初めて知った。
エルアンのおかげで、どんなに怖い状況に直面しても支え合える自信がついたのだから。
だから、次にフェレルマン公爵に会ったら、エルアンの言う通り、これまでぎこちなく接していたことについて正直に話そうと思う。