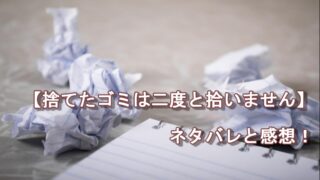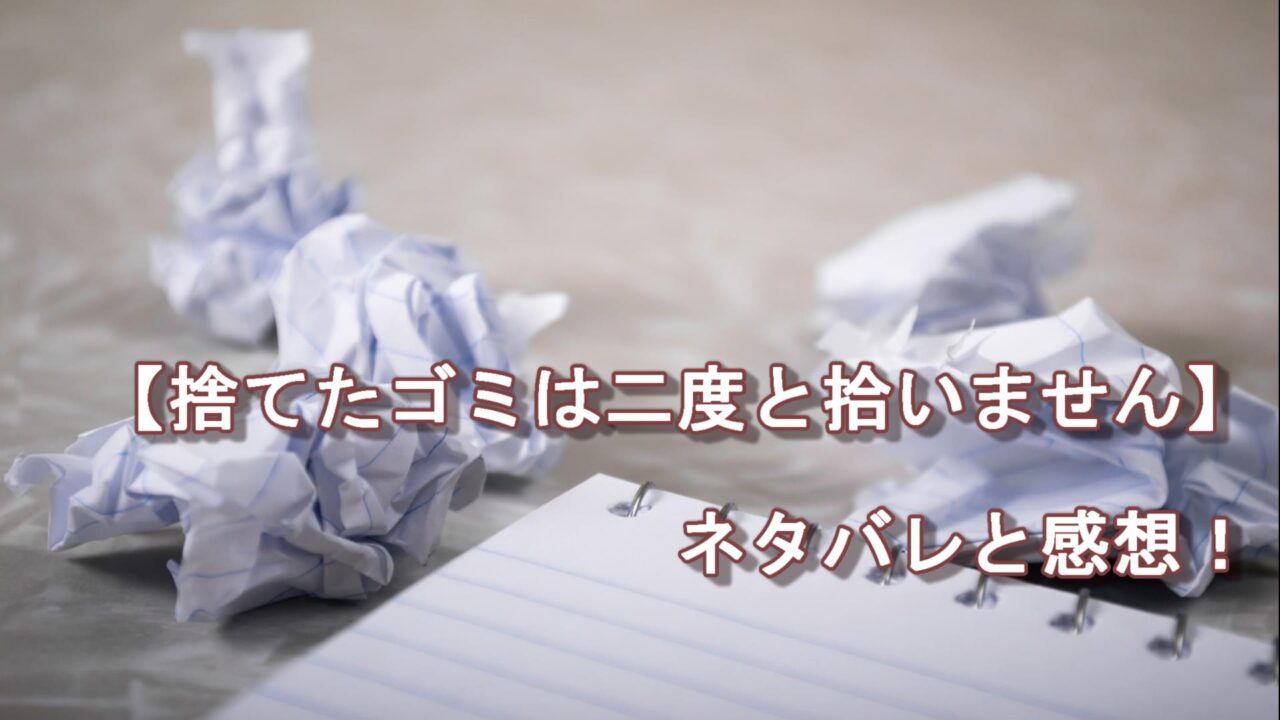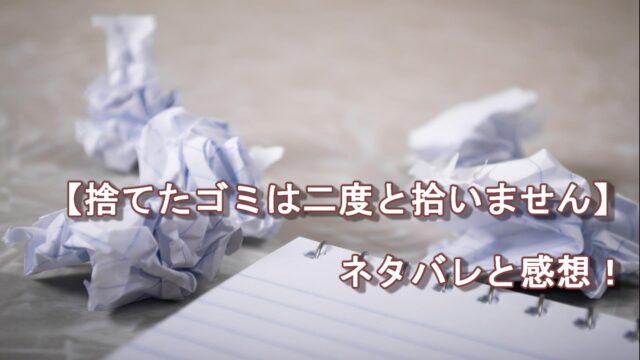こんにちは、ちゃむです。
「捨てたゴミは二度と拾いません」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

102話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 新年祭②
新聖国の使節団が到着したのは、新年祭が始まる前日の遅い午後だった。
他の使節団は祭りの数日前にはすでに到着していたが、ようやく現れたか。
「根性があるのか、それとも単に無鉄砲なのか。」
カリアンが口を尖らせてぶつぶつ言った。
私は黙ってカリアンに外套を差し出す。
「奴らはどこにいる?」
カリアンは外套を羽織りながら、デロント男爵に尋ねた。
「ルーン宮殿にご案内しました。」
「随行員の数は?」
「護衛騎士を除いた使節団は7名です。」
「思ったより多いな。王族が直々に来たのか。」
護衛団は通常、4〜5人で構成されるのが基本。
ステラ王女のように王族が直接来る場合は、その王族を護衛する貴族が数名同行するのが常だった。
「そこまで確認はしていませんが、確認してみましょうか?」
「いや、いい。直接行って見よう。」
外套を羽織ったカリアンが執務室を出た。
私とデロンド男爵、そして多くの侍従たちと護衛騎士たちがその後に続いた。
ルーン宮殿の前には神聖国から来たと推定される馬車があった。
召使いたちが忙しそうに荷物を運び、周囲では真っ白な制服を着た騎士たちが鉄壁のように守っていた。
威厳ある姿だ。
歩いていたデロント男爵が小さな声で教えてくれた。
「神聖国の神聖騎士たちです。神官のように神聖力を使うことができます。」
神聖力を使える騎士だなんて、珍しい。
「すごく強そうですね。」
「確かに強いですが、その分、癖が強いんです。」
「どういう意味で“癖が強い”んですか?」
「うーん、それをどう説明すればいいか……」
デロント男爵は少し悩んでから、苦笑いを浮かべた。
「他の人だったら、自分で体験してみてって言ってたところですよ。」
「直接経験しても関係ないですよ。」
「ダメです。あいつらが男爵に無礼を働こうものなら血を見ることになりますから、お願いです、あいつらとは関わらないでください。」
いったい何をどうするつもりなのか、こんなに反応するなんて不思議だった。
「気にしないでください。」
まるで心を読んだかのように、デロント男爵が厳しく言った。
「絶対に、絶対にあいつらと関わらないって約束してください。」
「わかりました。」
あそこまで堂々とされたら、嫌だとも言えず、私は仕方なく了承した。
デロント男爵と話しているうちに、私たちはルーン宮殿に到着した。
神聖国の使節団はルーン宮殿の庭園で私たちを待っていた。
神聖国だからなのか、使節団全員が真っ白なローブを着ている。
白い布の上に降り注ぐ陽の光がまぶしかった。
彼らに向かって歩いていたカリアンが、突然足を止めた。
慌てて止まった私はカリアンを見つめた。
「……陛下?」
デロント男爵が疑わしそうに彼を呼んだが、カリアンは答えなかった。
恐ろしい表情で神聖国の使節団をただじっと見つめるだけ。
「……驚いたな。」
そのとき、控えめに話しかけてきた。
「まさかあなたが直接来るとは思いませんでした。」
使節団の中で一番背が低い人物がフードを脱いだ。
肩の上に銀髪が柔らかく流れた。
髪色よりさらに淡い虹色の瞳がとても神秘的だった。
相手は成人の儀式すら済ませていないと思われるほど幼く見える少年だった。
これまでに見た使節団の中でも最も幼く見えた。
「私も正直来たくなかったんですけど、今回は私が直接行けって周りからすごくうるさく言われまして。」
声は壁に触れた泉の水が流れるように澄んでいた。
聞いているだけで心が洗われるような感じだった。
「だから仕方なく来ました。行かなきゃ世界が終わるって言われたんで。」
「陛下、それは一体どういう意味ですか……」
すぐそばにいた男が困惑しながら少年をたしなめた。
しかし、“陛下”とは?
その言葉は、あの少年が神聖国の王であり、教皇であることを意味していた。
そう考えるには、相手があまりにも若く見えた。
現教皇にして神聖国の王が即位してから、すでに20年が経っているのだ。
あの少年が同一人物だと考えるのは、さすがに無理がある。
しかしあの男が王でない者に“陛下”と呼ぶはずもない。
カリアンの態度もかなり深刻だった。
「……本当に、あの少年が神聖国の教皇なのですか?」
私は事実を確認するために、デロント男爵に小声で尋ねた。
「私もよく分かりません。教皇を見るのは初めてなので。」
デロント男爵も戸惑いながら小さく答えた。
「それにしても、なぜ教皇がわざわざ帝国に来たの?」
本当に教皇なのかもしれない。
そうなんだろうな。
私とデロント男爵は目で会話を交わした。
神聖国が新年祭に参加するために使節団を送ってきたことさえ驚きだったのに、教皇自ら来るなんて非常に異例のことであった。
教皇が単なる行事に参加するために自ら動くことなど、ほとんどなかった。
「理由は単純です。」
それほどまでに、神聖国が帝国の神殿たちに対し不正を警告しているのだと思っていたが、そうではなかった。
「カーディン帝国の皇帝陛下に、国婚を申し込むためにやって来たのです。」
・
・
・
神聖国の王は教皇の役割も兼ねていた。
そのため、神聖国の王は自身の子に王位を譲るのではなく、神に選ばれた者が王位を継承するのだった。
たとえ選ばれた者が赤ん坊であっても、新たに神の選択を受けた者が現れれば、即座に王位を譲るのが原則。
もちろん赤ん坊が継承するケースは稀だったが、現神聖国の国王であり教皇でもあるミスティオディス三世は、その稀な王位継承をした人物だった。
そういうわけで、年齢はまだわずか二十歳に満たなかったが、治世は20年を超えていた。
ミスティオディス三世が若く見えたのは、その長い治世に比べてのことだった。
ミスティオディス三世には2人の妹がいたが、そのうち1人は神聖国の貴族と結婚している。
まさか既に一度結婚した王女を相手に国婚を申し込むことはないだろうから、残る王女がその対象という意味だ。
問題は、その王女がまだ10歳にも満たないということだった。
カリアンの年齢は27歳だ。
二人の年の差はなんと17歳。
17歳差の夫婦がいないわけではない。
珍しくはないが、いないとも言えない。
とはいえ、相手はまだ成人式も迎えていない幼い子供。
年齢が近ければまだしも、あまりにも差が大きすぎる。
ミスティオディス三世は一体どういう考えで国婚を申し込んできたのか、気になった。
そしてカリアンがこの国婚を受け入れるつもりなのかも気になった。
神聖国は小さな王国だが、神の加護を受けており非常に豊かだった。
そのせいだろうか。
神殿を通じて他国にも影響力を及ぼすことができるため、外交的に見れば婚姻を受け入れるのもよかったが、やはり王女の年齢が引っかかった。
成人の儀式さえ終えていれば、ここまで気にならなかったかもしれない。
ずいぶん気を使ったが、私にできることは何もなかった。
外交上の問題が絡む政略結婚とはいえ、結婚というものは皇帝の私生活と深く結びついていた。
一介の補佐官である私が口出しできる部分ではなかった。
カリアンが私にどうすればよいか尋ねてくれたなら、まだよかったかもしれない。
内心ではカリアンが尋ねてくれることを願っていたが、彼は国婚については一言も語らなかった。
私はその事実にひどくもどかしさを感じた。胸が詰まるようでもあった。
直接聞いてみようか。
散々悩んだ末、結局は聞けなかった。
そうして時間が流れ、新年祭が始まった。
新年祭の初日は、皇帝の健在ぶりを国民に示す意味で街でのパレードがあった。
私がそれまで必死に騎馬の訓練をしていたのも、まさにこの日のためだった。
「騎馬服、よく似合ってるな。」
「ありがとうございます。」
ただの儀礼的なお世辞に過ぎなかったが、それでも気分はよくなった。
「今日の行事、うまくやれそうか?」
「もちろんです。陛下にご迷惑をおかけしないよう最善を尽くします。」
「どういう意味だ?」
カリアンは理解できなかったようで、首をかしげた。
「私が心配していたのは、あなたじゃなくて私自身なんです。」
「えっ?」
「正式な場に出るのは今日が初めてなんだ。だからうまくやれるか心配で。」
ああ、そうだったのか。
なんだかときめいた自分が恥ずかしくて、私は顔を伏せた。
頭の上でカリアンの低い笑い声が聞こえた。
「でも、行進が終わったら、もう以前のように外を歩き回ることはできないな。みんな僕のことを覚えてしまうだろうから。」
「髪を染めて、眼鏡をかければ分からないんじゃないですか?」
「いいアイデアではあるけど……僕は染められないんだ。」
カリアンはきちんとまとめられた自分の髪をそっと撫でた。
「この髪はブルードラゴンの祝福を受けた証だから、染毛剤が効かないんだ。魔法の染毛薬でも同じことだよ。」
ああ、それでこれまで皇帝は髪を染めず、こっそり外出していたのか。
「それなら仕方なくフードを被るしかないですね。」
「今は冬だからいいけど、夏はどうすればいいのか分からないな。」
トントン—
「陛下、すべての準備が整いました。」
「すぐに行こう。」
デロント男爵の報告に、カリアンはすぐに宮を出て馬に乗った。
私とデロント男爵もまた馬に乗った。
「よろしく、イレナ。」
手綱を握りながらそう言うと、分かったかのようにイレナが小さくいなないた。
「出発する。」
ギィィィッと、皇宮の門が開かれた。
カリアンを先頭に貴族たちが続々と行進に加わった。
新年祭の雰囲気に包まれた街には、たくさんの人々が集まっていた。
保育院の開館式の時とは比べ物にならないほどだった。
「わああああっ!」
「皇帝陛下、万歳!」
「カーディン帝国、万歳!」
人々の歓呼が街全体に響き渡る。
この時、カリアンが手を振ると、それに応じて人々の歓声はさらに大きくなった。
それだけ、帝国の民が皇室を信頼しているということだった。
その事実に心が温かくなり、自然と笑みがこぼれた。
次の行事のときは、もっと大きな喝采を受けたいという欲も少し湧いてきた。
そうなるように最善を尽くして補佐しなければ。
それが補佐官である私の役割なのだから。
私は堂々としたカリアンの背中を見つめながら、静かに決意を固めた。