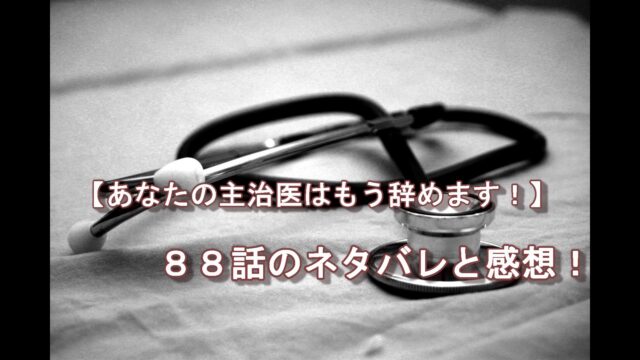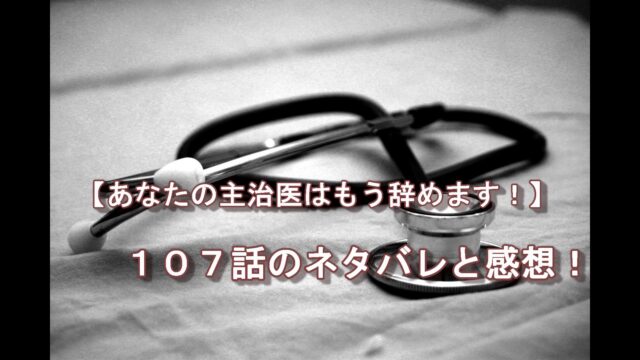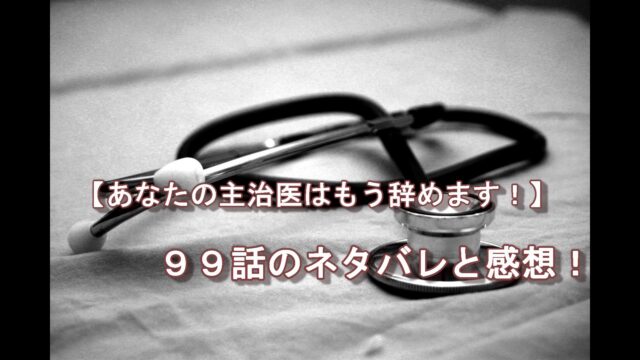こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

144話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- エピローグ②
「やはり……。」
父はため息をつきながら、額に手を当てた。
「3段ケーキを先に送った時点で気づくべきだったな。」
同じ姿勢をずっと取り続けるのは、一般の人にとっても大変だが、高齢の祖父には特に厳しいことだった。
それでも祖父は、絶対に席を離れないと頑固に言い張った。
「おじいさま、本当に大丈夫ですか?まずはおじいさまから描いてもらい、その後で休まれても……。」
「人生で最も幸せな瞬間だ。だから絶対に見逃したくないんだ。」
祖父はしっかりと席に座ったまま、私の手をそっと握った。
「おじいさま。」
祖父が何を考えているのか、なんとなく察することができたので、私は静かに囁いた。
「次に肖像画を描くときは、私の手ではなく、ひ孫たちの手を握ってください。」
せっかく巡り会えた家族なのだから、できるだけ長く一緒にいてほしい。
もうこれからは、父も私もずっとそばにいる。
だから、どんなときも一緒に過ごせる。
「みなさんお疲れでしょうが、休まずしっかり描いてください。」
レイビルはエルアンの背後でひそかに圧力をかけていた。
できれば私も味方になりたかったが、意外にもエルアンの肩を持ったのはディエルだった。
「平均的な詩人の五倍の報酬を受け取ったとか……。」
ディエルは心配そうにする私に対して、何も気にしていない様子で言った。
「まあ、そのくらいの監視は受けてもいいんじゃない?」
「……ディエル?ずいぶん資本の奴隷になったみたいだけど。」
「お金は魅力的なものだよ。……だからこそ、ペレルマン家に忠誠を、忠誠を。」
実の娘を見つけた喜びから、父はディエルに莫大な報酬を与えた。
そのせいか、ディエルは突然、物質至上主義に囚われた魂になってしまった。
「実際、何年分もの年俸を一括で渡したのだから、それだけで十分なはずだ。」
ペレルマンはすっかり気に入ったらしく、常に私たちの邸宅に入り浸っていた。
金を受け取って喜んでいるのとは別に、彼がペレルマンを気に入っているのは明らかだ。
そうして完成した肖像画は、私たち全員を満足させるものだった。
父はさらに一枚追加で注文し、首都にある自邸とペレルマンの領地のそれぞれの邸宅に飾ることにした。
そのほか、レイビルは私の肖像画を縮小していくつか制作する必要があった。
「24時間つきっきりというわけにはいきませんからね。」
父、叔母、祖父は、それぞれ肖像画を手に取りながら言った。
「離れていた時間が長かった分、そばにいるときはできるだけ一緒に過ごしたい。」
父は私の肖像画を懐中時計に入れ、医療研究所での仕事が忙しいときもそれを開いて見ていると言っていた。
まだ正式に整備されていない医療研究所の業務に追われ、父は相当忙しかったのだ。
すべてを投げ出して、家族と温かい時間を過ごそうかとも悩んだが……。
とにかく、私と生涯研究を共にするつもりなら、最初からしっかりと管理しなければと最善を尽くしていた。
いつか私もその研究所に勤務することになれば、今は一日中一緒に過ごしている祖父や叔母と離れる時間ができるだろう。
祖父も叔母も、私の肖像画を大切にし、それぞれの手帳やペンダントに収めていた。
肖像画一枚だけでも思い出がたくさん詰まっているのに、これから先、どれほどの大切な時間が積み重なっていくのか想像もつかない。
「リチェ、それじゃない?」
父はかつての黄室医療研究員たちが残した研究資料や、貴重な医学書を持ち帰り、私と一緒に議論することが多かった。
そして休憩のたびに母との恋愛話をしてくれた。
その話を聞くたびに、二人の愛の深さを再確認できるようで、私は嬉しかった。
「お前の母さんは、先に俺に告白したんだぞ。医学に没頭して女心も知らず、おまけに真面目すぎてつまらない男だったけど、なぜか気になって仕方なかったってさ。」
「……それって告白なんですか?それで、お父さんは何て言ったんですか?」
「そんなこと言われても、私はあなたが好きだって言ったよ。」
「お母さんが先に告白したんですか?」
「そうさ。でも、もう少し待った方がいいって言われるんじゃないかと思って、焦って言っちゃったんだよ。それにしても、僕たちってロマンチックじゃない?イザベルがケイルレンを初めて見たときのことを覚えてる?僕がそばにいたんだが……。」
お父さんはひとつ息を吐いて、話を続けた。
「ケイルレンに占いをしてもらったんだ。『今年中に素敵な女性と出会う運命だ』ってね。それを聞いて、僕は確信したんだ。これはもう、運命だって。だから今年中にお前を手に入れるって決めたんだ。まあ、そんなものより、僕たちの出会いの方がよっぽど美しかったけどね。」
ほとんど変わりはないように見えたが、お父さんは明らかに線を引いた。
そして、目をゆっくり閉じながら、声を震わせた。
「お前の母さんの遺体を直接検視したとき、どれほど泣いたかわからない。そのとき初めて、人生が崩れ落ちるという意味を理解した気がする。これからは、本当に彼女のいない人生を受け入れなければならない。でも、それが怖くて、明日が来るのが嫌だった。」
私は涙をこらえようと必死になった。
「でも、確かに彼女は出産した。それに、遠く離れた場所で赤ん坊が見つかって……娘が生きているかもしれないという可能性が頭をよぎった瞬間、私は母さんの後を追わずに済んだ。感情的になっていたわけじゃない。まるでロマンの主人公みたいに、そんな言葉を信じるものかと思ったが……。でも、それがイザベルの妹だとしたら、もちろん信じてたさ。」
お父さんは私の髪を優しく撫でながら言った。
「お前に会いたくてたまらなかった。伝えたいことが山ほどあったんだ。」
普段は誰に対しても厳しい表情の人だったけれど、昔話をしてくれるときのお父さんの顔は、今まで見たどんなときよりも優しくなっていた。
「お前の存在だけで、俺は狂わずに生きてこられた。どこかで生きているかもしれない、その事実だけが、俺を支えてくれた。本当にありがとう。」
私はお父さんの言葉を、胸の奥深くに刻んだ。
何度も想像してきたどんな家族よりも、最高だった。