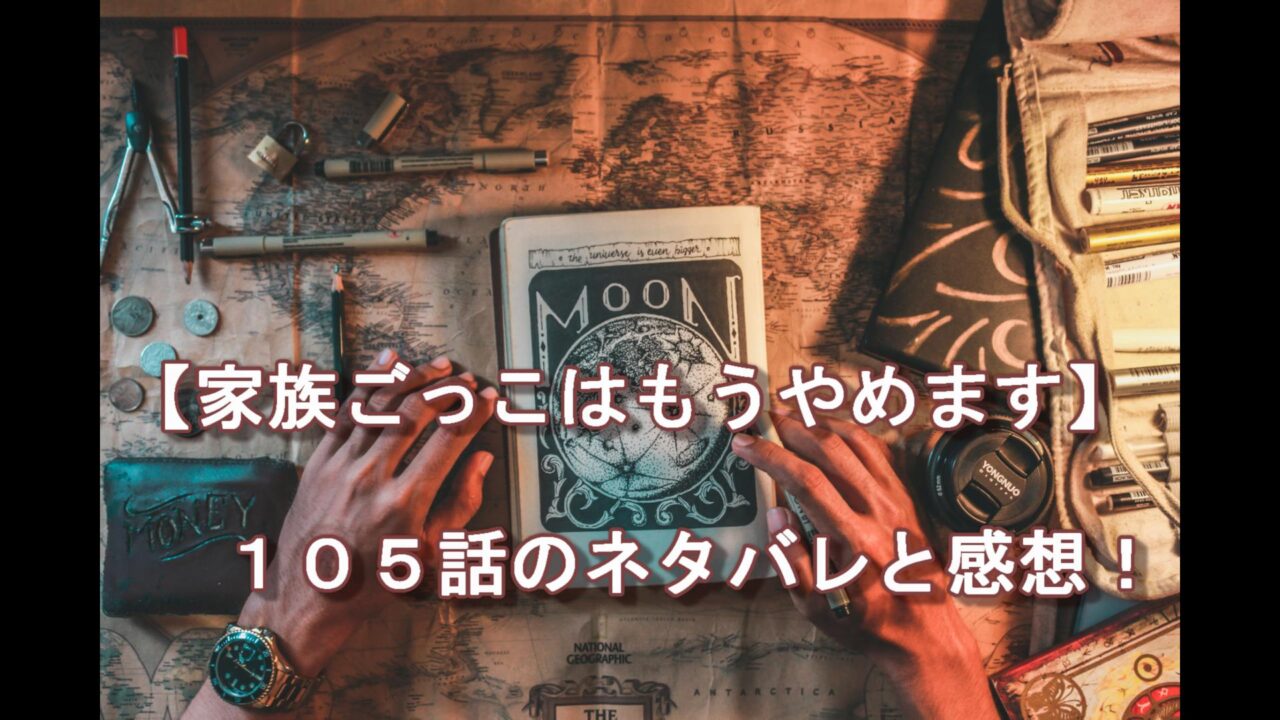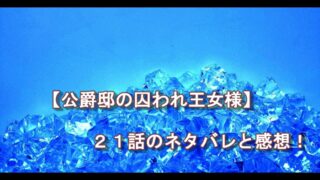こんにちは、ちゃむです。
「家族ごっこはもうやめます」を紹介させていただきます。
今回は105話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

105話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 黒い悪魔②
クリードは試合が始まると青い電撃で相手を一気に気絶させた。
電撃は見た目はかなり派手な魔法だったので、彼が大きな人気を得るのは当然のこと。
トーナメント8強から見物に来る貴族の数がぐんと増える。
そして準決勝の時は、お尻が重い大貴族たちが集まった。
そうして決勝。
皇族専用の席にユリッヒ皇帝が二人の妻とアレス、モニカを連れて現れた。
観客席が埋まり,決勝に勝ち上がった二人が姿を現す。
「あの黒い悪魔だ!」
観衆はクリードを発見するやいなや、しきりに「黒い悪魔」を連呼した。
もちろん、相手の魔法使いを応援する人も少数だが存在している。
「黒い貴公子!」
普通決勝まで来たらすごい実力者だったので、相手の魔法使いにも人気の証といえるニックネームがついていた。
「黒い貴公子」という別号に誰かが嘲笑う。
「黒い悪魔の、偽物が決勝まで来たね?」
「誰が偽物だ!」
「わざと黒いローブを着て、無理やりニックネームを作り出したあの魔法使いの話だよ。誰だと思う?」
「口に気をつけて。黒い貴公子は貴族だ、この野郎!」
「黒い貴公子」と呼ばれた男は、ある観衆の言葉通り、貴族家の令息だった。
長男ではないため、受け継ぐ爵位のない貴族も今回のトーナメントに参加したのだ。
彼らの中で結局生き残ったのは黒い貴公子、ステンリー侯爵家次男、バミロ・ステンリー。
バミロはくすんだ金髪とあまり悪くない外見で、それでもかなり人気を集めた。
「ステンリー侯爵家の次男が決勝まで勝ち進む実力者だとは知りませんでした、陛下」
ダイアナは春の女神が降臨したように美しい姿だった。
彼女はバミロを優しくユリッヒに称賛する。
「これを機に、良い人材を得られそうです」
ステンリー侯爵家はルチア公爵家の友好勢力である家門。
「ふむ、そうですね。ステンリー侯爵家にあんな人材がいるとは知らなかったな」
ユリッヒは戦争に勝利した上、今回のトーナメント大会が大変な人気を集めるようになり、
非常に気分が良い状態だ。
トーナメント大会がこのように人気を集めるようになった理由は、断然正体が分からない少年のためだった。
「本当に名前がクリードなのか・・・?」
クリード。
それは10年前に亡くなった次男の名前。
ユリッヒはすっかり忘れていた古い記憶を思い出した。
自分に似た壁の中と黒髪の女性、エステル。
いつも冷淡な表情と心の知れない態度のため、いつも好ましくない女だった。
(しかし、心が本当に深かった)
欲もなく、何事にも超然とした姿は、若い日のユリッヒにはつまらなく、面白くないだけの女性のように見えた。
特にダイアナのように毎日新しくて華やかな女性がそばにいるからもっとそう感じた。
これだけ歳月が流れて思い出してみると、あの女性は賢明なものだった。
(ただ家門の災いを避けることができなかっただけだった)
子供を持った時は、しばしばその冷たい表情に柔らかい笑みを浮かべたりもした。
本当に懐かしい昔の時代に、ユリッヒはかすかな気分に浸り続ける。
相変わらず愛しているが、時々疲れを感じるダイアナ、皇后を過度に恐れて小心なソフィア、二人ともちょっとうんざりした。
何かまた新しいものがあればいいのに。
(戦争をもう一つ行えば大丈夫かもしれない)
次の戦争は生意気な魔導王国カラディスと戦い、徹底的に踏みにじらなければならない。
そうすれば、エデン帝国は大陸最強の帝国として完璧に位置づけられるだろう。
その時、決勝戦を行う2人のライバルが向かい合って握手を交わした。
観衆は競技場が離れるように応援しながら大声を上げた。
その熱い雰囲気とは違って、コロシアムの中央には台風の目のように沈黙が流れている。
クリードが手をこまねいて振り向くと、バミロは突然声をかけてきた。
「子供よ、私に勝つことは考えずに適当に抜けた方がいい」
クリードは無感覚な目つきでバミロを見上げる。
「この舞台は皇后陛下が私のために作ってくださったのだ。とんでもないことだが、君が私に勝ったら皇室が君を放っておかないだろう。もちろん私の家門も」
「・・・」
クリードが黙っていると、バミロは自分の脅迫がうまくいっていると思った。
「しかし、残念に思うな。私があなたを私の家の魔法使いとして雇ってあげるから」
そこまで話が出た時、クリードは我慢できず、可笑しそうにニヤリと笑ってしまう。
それから、首を斜めに傾けながら、爽やかに答えた。
「嫌だ」
バミロの表情はこわばった。
今まで彼がスタンレー侯爵家の次男だということを知った人たちは皆礼を尽くした。
しかし、クリードは礼儀どころか、自分を嘲笑うではないか。
「お前・・・まだ幼くて道理が分からないようだが、これがどれほど光栄な提案なのか・・・」
バミロの言葉は後を絶たなかった。
「黙り込んで実力で証明しなさい。自信がなければ棄権するか」
クリードが面倒くさそうに彼の言葉を切ってしまったからだ。
バミロの顔が真っ赤に染まる。
「よくも、私にこんなことをしても無事だと思うか!」
クリードは自分を教えたラルクの言葉を思い出した。
『とにかく貴族の子たちは傲慢だ』
彼の最初の師匠、ラルクの言葉は概して本人の自慢で、少し聞きたくないところもあったが、間違った言葉は一つもなかった。
特に、今のような状況では。
「お前こそ無事だと思うか?」
クリードは何でも早く学んで習得した。
それを適材適所に使用して応用することも優れているし。
バミロはかっとなってクリードに向かって指を差す。
「くそ・・・!幼いと大目に見ようとしたら、そうではないようだ!」
そして試合が始まった。
「死ね!」
クリードの気性の荒い効果は並外れたものだった。
バミロは最初から全力を傾けてクリードを圧殺しようとする。
そうしても、すべての攻撃がクリードにはつまらなく見えた。
(ネロ兄さんが実戦のように訓練してくれると飛びかかってきたことに比べれば、あまりにもつまらなくて欠伸が出るほとだよ)
クリードのローブは魔法の影響で派手に宙を舞う。
しかし、反撃はなかった。
「反撃しろよ、黒い悪魔!」
「いったい何をしているんだ!」
人々はクリードを大声で応援していて彼がすっきりした試合を見せてくれないと、一人二人とブーイングを浴びせ始める。
「私がこんな試合でも見ようとお金を使ったと思うのか!?」
「早く攻撃しろよ、あのろくでなしめ!」
「私の掛け金を無駄にするつもりなのか?」
そのようにブーイングの音と黒い貴公子を連呼する声がコロシアム内部を埋め尽くすと、バミロはさらに得意になった。
「もう本当に終わらせてやろう!」
クリードは避けていた動きを止める。
彼の頭の中に世界で最も美しい楽器の音のような声が響き渡った。
(人々は劇的なことが好きだ)
バミロが攻撃し、クリードは逃げなかった。
(望んでいた場面を待っていて怒った人たちを一気に静める方法が何か分かる?)
今までかぶっていたフードが後ろにさっとひっくり返る。
ローブは魔法にかけられて敗残兵のマントのように裂け、宙をはためかせた。
ポン!
彼の顔を半分隠していた仮面が床に墜落する。
(彼らの予想を超える素敵なものを見せればいいんだよ」
顔が丸見えになったクリードが顔を上げた。
日差しが差し込んだ瞳に青い眼光が宿る。
バミロの魔法に引き裂かれたローブが風になびいた。
そのローブと同じくらいクリードもめちゃくちゃになるのが普通だった。
しかし、彼はまったく元気だった。
小さな傷一つもなく。
「ど、どうやって・・・!」
バミロは渾身の力を尽くした攻撃が少しも通じなかったことに気づき、思索になった。
それで終わりではなかった。
「あれは・・・!」
濃い青の魔力が空中に数十本の線を描き、クリードの周りにぐるぐると周り始める。
今までクリードの能力は電撃魔法として知られていた。
しかし、あれは電撃ではなかった。
「あれは何の魔法なの?」
観客席が混乱に陥った。
その時、ユリッヒが席から飛び起きる。
「陛下?」
ダイアナが怪しく呼ぶにもかかわらず、ユリッヒは返事もせず、すぐ前に走るように近づいた。
「ありえない・・・!」
彼の怯えた覗線はクリードに向けられていた。
まるで森の真ん中に落ちたように、清らかな香りが自分を包んでいた。
自分の代わりに死んだ実の兄と同じ、魔力の香り。
「クリード!」
皇帝はあの少年が自分の息子であることに気づく。
しかし、彼の叫びはクリードが立ったところまで届かなかった。
クリードは無表情な顔で、間抜けな表情をしているバミロに向かって、ただ手を伸ばす。
すると、魔力が彼の意志に反応した。
魔力が周囲を襲うと狂風が吹いた。
青い魔力がものすごいスピードで形を整えていく。
それはついに観客席まで伸びた巨大な塊になった。
皇帝の小物感が凄いですね。
自分の息子だと気づいた皇帝は、クリードをどのように対応するのでしょうか?