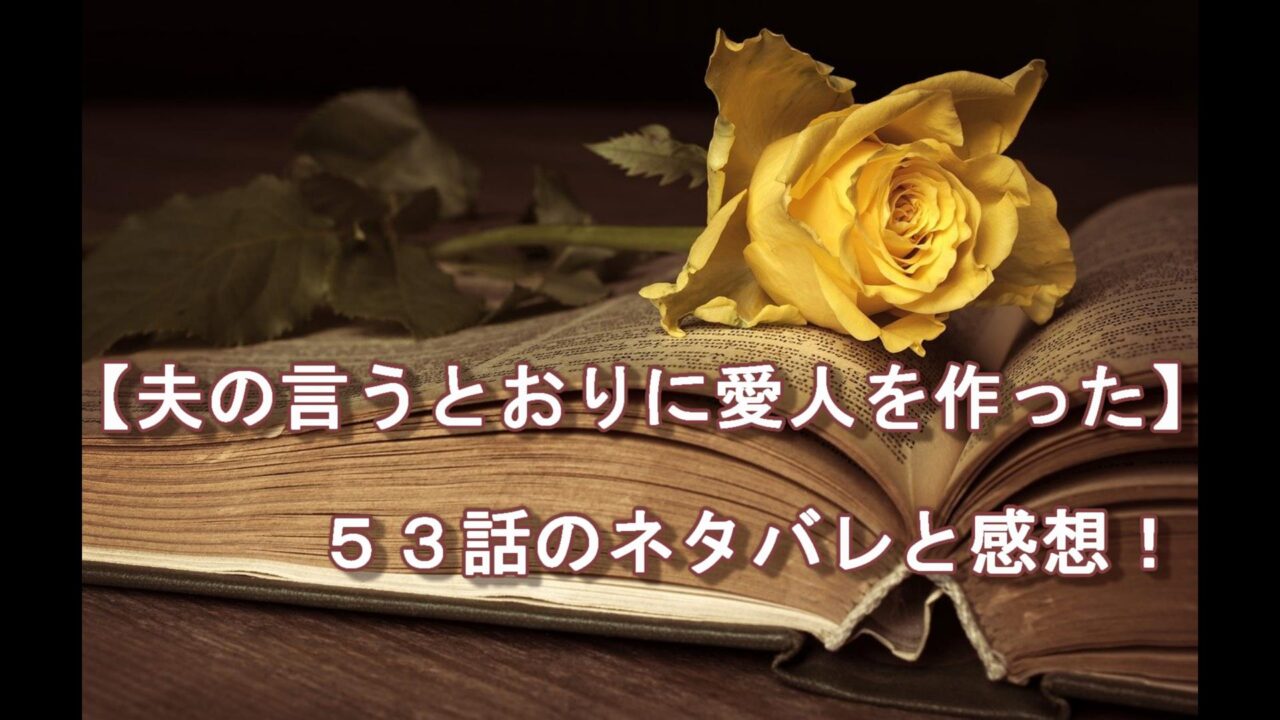こんにちは、ちゃむです。
「夫の言うとおりに愛人を作った」を紹介させていただきます。
今回は53話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

53話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- セルベニアでの出会い②
3人は日当たりの良い2階の応接室に席を移した。
長いソファーが向かい合った構造なので、片方にはエドワードとルイーゼが一緒に座り、向かい側のソファーにはロレインが一人で座る。
久しぶりに座る柔らかいベルベットのソファの感触感にルイーゼは心地よい笑みを浮かべた。
「ふむふむ、私が無格にふるまいましたね。このブローチは確かにアレン・ディ・セルベニアのものです」
ロレインはまっすぐな姿勢でテーブルの上にブローチを置いた。
彼女はすぐに不満そうな目でエドワードを見つめた。
「殿下はこんなふうに小細工をするんですね」
「小細工ではありません」
エドワードは例の笑みを浮かべながらルイーゼを見る。
「私はこのような状況を、縁あるいは運命と表現しますが」
「どう見ても人質に見えますが」
「叔母さん、違います。エドワードは私の友・・・」
「友?」
ルイーゼはしばらく悩んだ。
エドワードに露骨に敵対的な叔母が、彼女にだけは初めて会う仲であるにもかかわらず、悠々と振る舞っている。
それなら、エドワードと自分が親しい間柄だという事実を強調すれば、彼女もエドワードをよく見るのではないか。
ルイーゼは自分をとろけるような目つきで見つめるロレインを眺めながら、慎重に唇を離した。
「・・・友達みたいな恋人です」
「恋人だって?」
ロレインは今度エドワードを見た。
エドワードは一瞬驚いた顔をして、すぐに表情を整える。
彼が興味深いように笑った。
「そういうことになりました」
「は」
ロレインの顔は一瞬にしてしわくちゃになった。
彼女はエドワードを冷酷な目で睨みつける。
「殿下は純真な子を利用してでも、どうしてもこのセルヴェニアを手に入れたいようですね?」
「まあ、誤解があるようだが。私はセルベニアとは別に、ルイーゼさんに真剣な気持ちです」
エドワードは片腕をそっとルイーゼの肩に置く。
ルイーゼは驚いて彼の顔を見た。
エドワードはまっすぐな顔で前を向いて微笑んでいる。
「懐抱を開く前に重要なことは先に解決したほうがいいです。領地を見ると、前とは雰囲気がかなり変わったようですが」
「話を変えるには。それでも、それはちゃんとご覧になったに違いありません」
ロレインの表情は真剣にこわばった。
「半年前からある疫病が出回り始めました。急に眠りに落ちて目が覚めない病気で、原因は分からないが、偶然に目が覚めるのを待つ以外に他の方法がありませんでした。セラピスト一族という名前が顔負けするほど、その病気にかかった人々からいかなる共通点も見当たりませんでした」
「目が覚めない病気・・・」
ルイーゼはマクシオンを思い浮かべながら呟く。
「たぶん、副官が目を覚まさない理由もそのためのようですね。私たちは睡眠病と呼んでいます」
「当主が病気だということは、その睡眠病のことですか?」
「はい」
「病気というより、黒魔法のようでしたが」
エドワードの言葉にロレインが驚いたように両目を大きく開けた。
「黒魔法だなんて。うちの領地にいったい誰が・・・。確かに,うちの家も恨みをたくさん買いましたが」
「セルヴェニアが恨みを買ったんですか?」
ルイーゼは驚いた顔で尋ねる。
ロレインがエドワードに接していた時とは全く違う表情で彼女の質問に優しく微笑んだ。
「セラピストだからといって、すべての人を救うことはできない。犯人は多分うちの家門に悪い心を抱いている誰かだろう。本来、人を治療する職業は人を生かすほど多くの命を送ったりもするんだよ。身近な人を失った人たちは、責任を負うところが必要だ」
「そんなことが・・・」
ロレインはエドワードの方を向いて話し続けた。
「黒魔法とは、今になってちょっとぴったりですね。病気というには釈然としないところが多かったですから。私たちの領地には粗末な魔法使いがたびたび立ち寄ることを除いては、黒魔法どころか魔法とも関連がなく、そちらには門外漢の方です。領地の近くでしか起こらないので、一種の風土病だと思っていたのですが・・・」
「汚染された魔法石を除去すれば、被害者はこれ以上出てこないでしょう。それは滞在させていただいたお礼として、今日中にこちらで処理いたします。ただ、魔法の解除が問題なのですが。領地内で睡眠病を発症した人と完治した人のリストを調べさせていただけますか?セルベニア夫人なら記録しておいたと思いますが」
エドワードが平気で笑うとロレインは渋い顔をする。
「はい、まあ。それは難しくありませんが、どのように解決するつもりですか?」
「きっと眠っている人たちには共通点があるだろうから、まずはそれを探してみるつもりです」
エドワードはルイーゼを見つめながら低い声で付け加えた。
「書類は私がのぞいてみるから、ルイーゼさんはその間、家族に会ってみてください。叔母さんと話したい話が多いと思うんだけど」
「ありがとう」
エドワードはルイーズをじっと見つめ、素敵な笑みを浮かべた。
ルイーゼの顔にピンク色の紅潮が降り注いだ。
「・・・」
ロレインは2人の姿をじっと見つめ、すぐにため息をついた。
セルベニアの城は実用性を強調し、やや地味に見える外観とは違って、内部は古風に飾られていた。
セラピストの家門らしく傷の回復を助けるという高価なリベン木で作られた内部は、全体的に原木特有の暗褐色だったが、床に明るい色のカーペットが敷かれていて暗くない雰囲気を醸し出している。
エドワードが割り当てられた部屋に向かうとロレインはルイーゼに向かって、まるで久しぶりに会った間柄のように思う存分喜んだ。
ルイーゼは初めて見る叔母がぎこちなかったが、嬉しい反応が嫌ではなかった。
「もしかして従兄弟にも会ってみることができますか?」
「もちろん」
私的な話が長くなったため、使用人を呼んだロレインは直接燭台を持ってルイーゼと一緒に廊下を歩く。
夕焼けの光に沿って廊下に窓の形の影がついた。
「セルベニアアカデミ一時代にあなたのお父さんとは首席を争ったんだ。友逹よりはライバルに近い間柄だったわ」
「お父さんと叔母さんがですか?」
「そうだね。一度だけ除いて、私はいつも次席だったんだけど。成績表が出るたびにからかってきた姿がどれほと憎らしかったか。生きているという知らせを受けて嬉しかったが、その連絡がまもなく死ぬという知らせだったわ」
「・・・そうだったのですね」
ルイーゼは沈んだ顔で視線を落とす。
「大陸最高の治療師も治療できない病気にかかったと平気で手紙を送ってきたが、すでに死んだと思っていた人が生きているとは、それさえも嬉しくはあった。私があいつを喜ばせる日が来るとは思わなかったが」
ロレインは廊下に立って窓の外をじっと見つめる。
夕日の光が染み込んだ彼女の瞳は、遠い過去を辿るようだった。
彼女の笑顔はとても自然で穏やかで、ルイーゼは何も言わずにロレインを望んでいる見るだけだった。
「娘がいると話していたわ。大人になるまで、もしかしたらその後も彼らが過ごすそこで暮らさなければならないかもしれない子供が。妻は子供を守るために家門にも、世の中にも秘密にすることにしたそうだね」
「・・・」
「そこがペリルスだとは思わなかった。守るって何よ、危険なところにあなたを置いて彼らだけが去ると思っていたなら、とっくにあなたを探していたのに・・・」
「それでも一緒の時はいい思い出がたくさんありました。両親がそこを選んだのは、おそらく私が知らない他の理由があったのではないかと思います。たとえ一人残された後には耐え難い所だったとしても・・・」
「それなんだけど、ルイーゼ。出征のような危険なことはさておき、セルベニアに定着するのはどう?」
「え?」
ルイーゼは驚いた顔でロレインを見た。
「私はこの家に入ってからずっと女の子が生まれることを望んでいたわ。紫色の目をした女の子は本当に愛らしいだろうと思った。君が持っているその目はセルベニアの象徴とも同じ色なのよ」
ロレインはルイーゼの紫色の目をじっと見つめる。
「やっと生まれたというその子をあなたのお父さんが隠して一生見られないようになったので、本当に残念だったわ。君が直接訪ねてきてくれてどんなに嬉しいか分からない。大きい男たちは可愛い味がないじゃないか。だからといって私の息子に大きな不満があるわけではないけど」
「あ・・・」
ルイーゼは混乱した顔で答えを悩んだ。
一人は嫌だった。
レイアードのそばにいたのもそのためで、エドワード、マクシオンと一緒にいることにしたのも寂しくなりたくなかったからだ。
もしかしたら、彼らを簡単に許すことができた理由も、実はまた一人になるかもしれないという恐怖のためかもしれない。
呪いを解除することはできるのでしょうか?
マクシオンも早く目覚めてほしいです。
叔母からの提案に、ルイーゼはどのような返事をする?