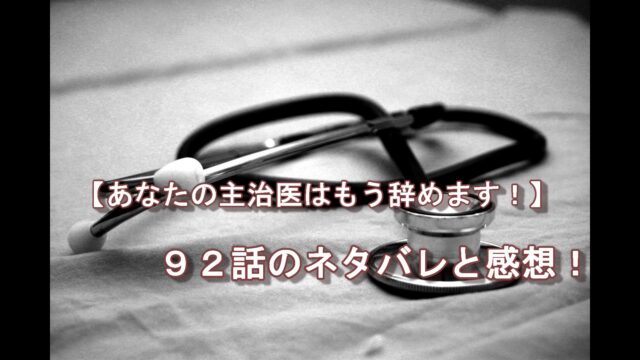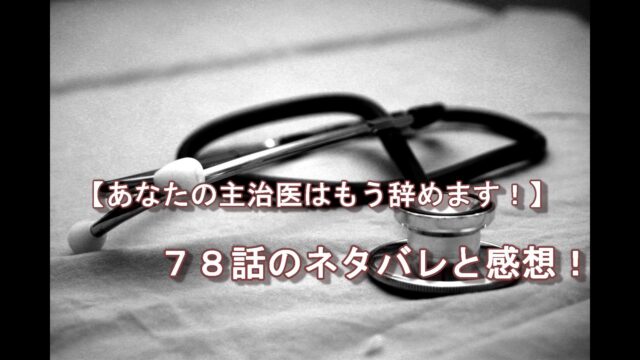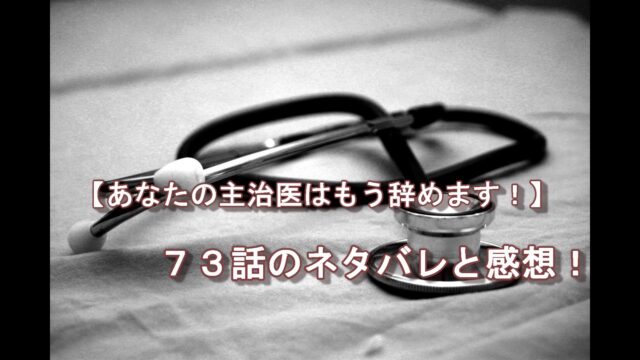こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

132話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 皇室裁判③
「ハエルドン・メベス・アーロハイメン王子、そしてリチェ・シオニー・フェレルマン令嬢。」
皇族用の席の最前列に座っていたハエルドン王子が立ち上がり、正面の席に向かって歩き始めた。私も同じように立ち上がり、階段を降り始めた。
フェレルマン家の令嬢が娘を探しているという噂はいつの間にか首都中に広まっており、私がやや長い階段を降りていく間、周囲の人々は興味津々とした様子で私を見つめていた。
かつて市場での大会の時に私を見たことがあるという人々は、「やっぱりあの時の女性がフェレルマン家に似ているから……」といった言葉を隣の人と交わしていた。
「事件の内容は非常に簡潔だ。フェレルマン家のあなたが建国祭のとき、イセラ皇后に有害な処方をしたというのは本当ですか?」
皇后は、この全ての事を早く終わらせたいのか、ためらいもなく質問を投げかけた。
皇室裁判はその名の通り皇族が進行するものであり、厳格に定められた形式はなかった。
ただ、出席する貴族たちが満足できるよう注意を払い、適切に進行しなければならなかった。
イセラ皇后はジェンシー公妃の隣で静かに手を握りしめていた。
ハエルドン皇子とは隔離されている状態で、このすべての状況が現実感を失わせる要因となっていた。
「いえ、私は本当に妊娠に有利な処方をしただけです。私が有害な処方をしたという証拠でもあるのですか?」
もちろんそんなことはありえなかった。
ハエルドン皇子は、平民である私に対して何の疑いも後ろ暗い意図も持っておらず、厳しい罰を与えるつもりなどなかったはずだ。
「当時、私の処方内容をすでに調査官に提出しましたが、改ざんの可能性があるため正式な証拠として使用できないと言われました。」
私はすべての準備を整えて臨んだが、ハエルドン皇子側はまだ状況を十分に把握できておらず、かなり動揺している様子だった。
「それでは、ハエルドン皇子が直接訴えを起こした理由を話してみてください。」
皇后の言葉に、ハエルデン皇子は困ったような顔で答えた。
「皇后が服用していた薬にポプリの花が含まれていたようです。」
「そうだったんですか……証拠はありますか?」
ポプリの花は、妊娠を妨げる薬草の一つであった。
「そのような噂があり、皇后様が服用していた薬を調べたところ、ポプリの花が含まれているようでした。」
「なるほど、薬を調べてポプリの花の成分を見つけるとは、慎重な研究テーマですね。皇室医療研究者としての未来が明るいですよ。」
私は少し皮肉を込めた後、素早く話題を本題に戻した。
「噂が本当かどうか、その推測が正しいかどうかは薬を調査すれば分かるでしょう。私が処方した薬はまだ残っていますか?」
私はイゼラ皇妃に問いかけた。
薬が隠されているわけではないにしろ、調合が改ざんされていれば中に証拠が残っている可能性があるが、既に全て飲み干したのなら調査する術はない。
「全部飲んだわ。だから残っていない。」
イゼラ皇妃は目をそらしながら答えた。
状況を十分に理解していない様子ではあったが、とりあえず夫の立場を守るためにその場を収めようとしているのは明白だ。
「でも……君が処方した薬を飲んでから体調が良くなかった。」
「まあ。」
その言葉に驚いて目を丸くしたのはジェンシー公妃だった。
「妊娠じゃない?私がリリーを授かった時もまさにその症状だったわ!リチェ様の腕前を考えると十分あり得ることよ!」
私は口を閉ざして黙っていた。
体調が良くないというのはあまりに漠然とした概念であり、それだけで妊娠の兆候と断定するには無理がある。
『そもそもイゼラ皇妃は体が弱く、妊娠する可能性はほとんどないのに……。』
しかし、今その事実を明らかにする必要はなかった。
「イゼラが勘違いしているのではないか?リチェが悪い処方をするなんて考えられない。」
ジェンシー公妃は私の味方についてくれた。
結局、この件に疲れていた皇后が話に割って入った。
「とにかく、証拠もなく噂だけで訴訟を起こそうというのか?」
「そうですね。」
ハエルドン皇太子は、皇后の言葉に含まれた冷淡な怒りを察知し、急いで答えた。
「認めます。私が軽率でしたね。お互いに誤解があったようなので、この辺りで和解するのが良いでしょう。」
自分が予想していなかった状況を早く収束させたいという彼の気持ちがはっきりと見て取れた。
「まあ、実際にポプリの花を摂取したとしても、生命に大きな影響があるわけではないのですが……。」
ハエルドン皇太子は笑みを浮かべつつ続けた。
「観衆を納得させる形で、簡潔に結論を出して、この件をこれ以上拡大させることなく、この裁判を終えたいものです。」
彼は私の顔を見ず、皇后だけを見つめて言葉を続けた。
「私も皇太后の件に軽率に対処し、噂話だけを信じて事を大きくしてしまった点について謝罪します。」
彼は誠意がないにもかかわらず、あたかも悔恨の気持ちを表しているかのように振る舞った。
「そして、フェレルマン令嬢についても、皇族に証拠の残らない薬品を処方した件に対して反省しているという簡単な謝罪だけで十分かと思います。皇后陛下はどうお考えでしょうか?」
最後まで自尊心を守りながらも、私に謝罪を求める形で結論を締めくくろうとするその姿勢には、計算された意図が感じられた。
皇后はこの面倒な場を早く終わらせたいのか、冷静に返答した。
「双方に特別な証拠がない以上、それでも構わないでしょう。」
傍聴席の人々は、想像以上に裁判があっけなく終了したことにざわつき始めた。
私は落ち着いた声で話し始めた。
「皇太子殿下が寛大にご配慮くださったおかげで身の潔白が証明されましたが、これほど厳しい捜査になるとは予想しておりませんでした。証拠が十分に残らなかった点、深く反省しております。今後は処方の際に必ず処方記録と本人の署名を確実に保管するよう努めます。」
ハエルドン皇太子は呆れたような顔で私を見たが、何も言う間もなく私は再び話を続けた。
「ところで、これほど多くの方が集まっている機会を利用して、他の議案について話し合うことはできないでしょうか?」
「他の議案とはどういう意味だ?」
「はい。私が万が一、不当な濡れ衣を着せられることがないよう、皇室医療研究陣にお願いして皇族の薬物投与記録を公開しました。あ、そちらは調査官の方が保管されています。」
「皇族薬物投与記録」という言葉に、ハエルドン皇太子の顔色が少しだけ変わるのを見て、私は小さく笑った。
「見てみると少し奇妙な点があるので、この場で議論してみたいと思います。」
「……興味深いな、フェレルマン嬢。」
ハエルドンは私をじっと見つめながら言った。
「今、君は被告としてこの法廷にいるのに、一体何の権利で他の議案を持ち出すのかね?」
「私はフェレルマン嬢の別の議案を聞いてみたいですね。」
その時、ジェンシー公妃が立ち上がり、ハエルドンを見つめながら話し始めた。
「皇后陛下、個人的に私はリチェ嬢に多くの助けをいただき、その能力と人格を信じています。フェレルマン嬢がこの場で議論すべきだと判断したのであれば、必ずそれに値する理由があるはずです。どうかフェレルマン嬢の発言を許可してください。」
これが、私がジェンシー公妃を遠くから呼んだ理由だ。
私が発言できるよう頼んだお願いを忘れず、助け舟を出してくれた彼女に、私は一度感謝の眼差しを向けた。
「よろしい、許可することにしよう。」
皇后はハエルドン皇子よりも、私に肩入れしているジェンシー公妃の意見をもっと聞きたいと思ったのか、冷静に答えた。
「では、19年前に皇室医療研究所に所属していた私の父を参考人として招いてもいいですか?この記録についてもっと詳しく説明していただけると思います。」
「許可する。アルガ・エイト・フェレルマン氏を前に進ませなさい。」
「ありがとうございます。」
父は私を見つめた後、外した眼鏡をかけ直し、堂々と前に進み出た。
そして、静まり返った傍聴人たちに向かって話し始めた。
「19年前、腹痛や頭痛を一度に解消できる薬物を研究していた。その研究結果をすべて医療陣に提供したが…」
父は調査官に渡していた報告書を手に取り、それを掲げながら薬の構成を一つ一つ説明し始めた。
「そして、本当に運命ともいえる形で、私の娘リチェがセルイヤーズ公爵家に仕えることになりました。そしてリチェは、幼いエルアン公子様に投与されていた毒を発見しました。」
セルイヤーズに投与されていた薬の調合者が誰だったのか知らなかったのか、ハエルドン皇子の顔は一瞬固まった。
すると突然、裁判所の扉が開き、誰も予想しなかった人物が入ってきた。
それはまだ血のにじむ衣を身にまとったままのジェイドだった。