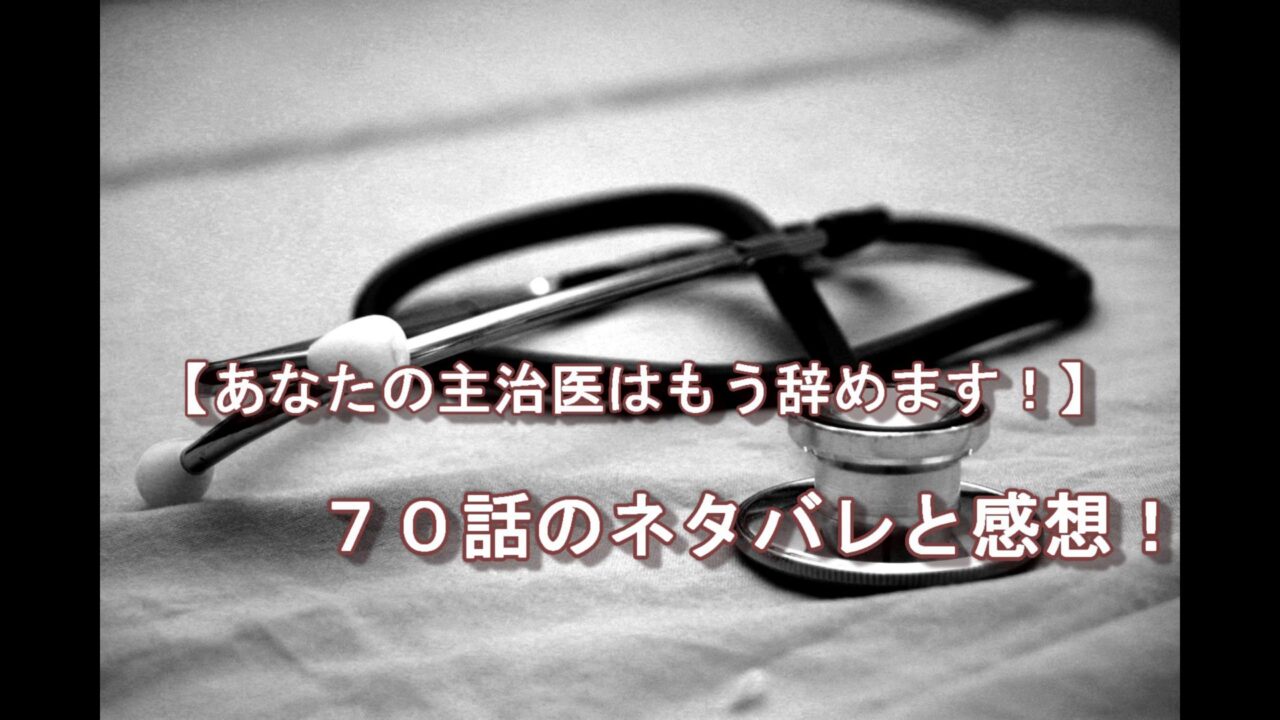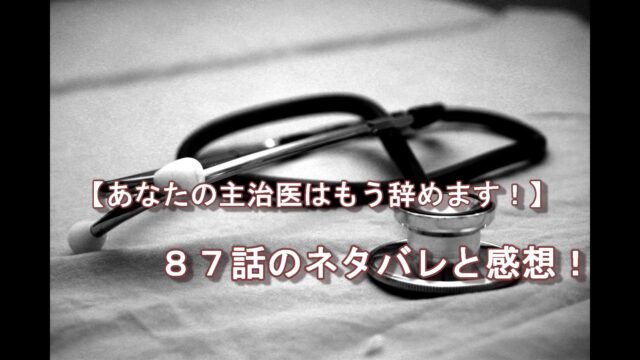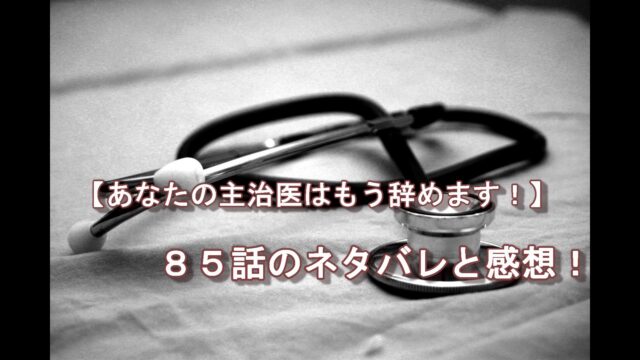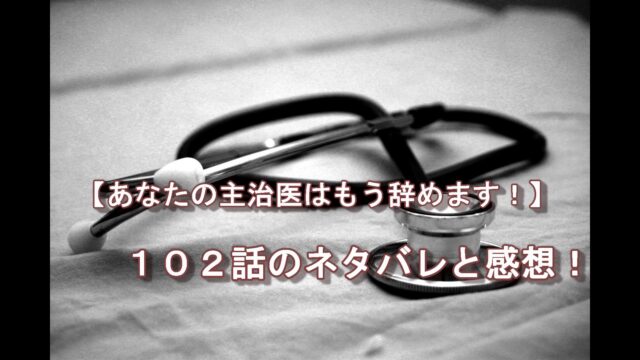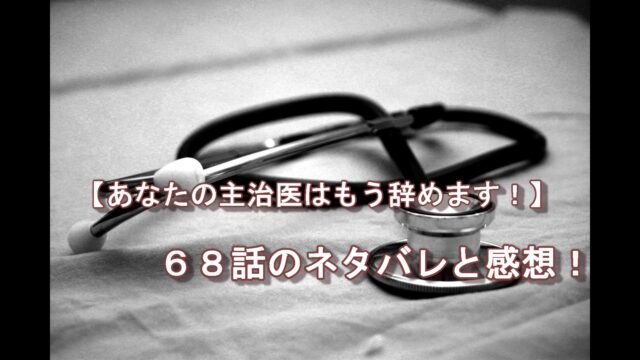こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
今回は70話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

70話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 閉会式
閉会式の日。
天気は睛れていて、近づいてきた夏によって日差しは強かった。
狩猟大会の1位はエルアンが占めた。
この狩り大会を通じて、エルアンは堂々と全帝国にセルイヤーズの存在感を知らせることに。
今では誰もセルイヤーズの後継者にうっとりしていたり、自分の役目ができないという話をすることができなかった。
「適当な差で皇太子さまに負けてさしあげればいいものを」
フェレルマン子爵は舌打ちをして私のそばでつぶやいた。
「社会生活があんなに下手だからだよ」
「・・・誰かが聞いたら子爵様は社会生活が本当にお上手な方だと思います」
「私が下手だから言うんだよ」
不思議なことに、フェレルマン子爵はエルアンに対してかなり否定的な立場を取っているようだ。
確かに、私が知っているすべての人がエルアンを気まずく思っている。
実母のイザベル夫人までもだ。
「私もハエルドン皇子様に絶対負けてあげなかったから、とても疲れていたよ」
「ハエルドン皇太子様とジェイド皇太子様とは違いますからね」
「そう、ずいぶん違うような気がした」
フェレルマン子爵はうなずいた。
「ところで研究室のナタリーか?あの子と対決したんだって?」
「はい」
「詳しいことは聞いていないが、それでも念のため君の患者を見ることは見た」
「ハリフィ・ヒキガエルの毒ですよね?」
「あれをナタリーは何と診断した?」
「トマソ症候群です」
「具合が悪いね」
「研究室の実力は元々そうなんですか?」
「研究チームの問題ではなく、我々が頭が良すぎて生じる問題だ」
「なるほど」
私は快く同意し、皇帝から下賜されるエルアンの姿を見る。
もう私の役割はほとんど終わった。
ウェデリックを渡したのだから、勝手にイシドール男爵も処理するだろうし、あのように凛々しく育ったのに、セルイヤーズ令息を守れない理由がなかった。
天気が肌寒くなる季節の変わり目に、本当に元気なのか確認さえすれば、私のやるべきことはすべてやったわけだった。
実際、それさえもフェレルマン子爵に渡せばいいのに・・・すぐに狂いそうで、私の成人の誕生日パーティーにでも捕まえておかなければならない人にそれまで望むことはできなかった。
「私の主治医、リチェ・エステルがいなかったら、私はこの場に立つことさえできなかったでしょう」
エルアンが、いつの間にか感想を述べていた。
私はまだ成人していないので、主治医だということには語弊がある。
しかし、フェレルマン子爵が公爵城についていないことを誰もが知っていて、皆が認める雰囲気だった。
「この栄光をすべてリチェ・エステルに捧げます」
拍手が沸き起こると、フェレルマン子爵が不満そうに言った。
「リチェ」
「はい」
「あいつ、ちょっと変じゃないか?
「・・・あいつだなんて。公爵様ですよ」
「あなたにとっては、特にちょっとおかしいと思うんだけと。あなたのことが好きすぎると思う」
「好きにならない理由がありますか?私のおかげで、あそこにああやって立っていられるのは正しい話じゃないですか」
「それはそうだけど・・・」
「そして昨日もご覧になったじゃないですか。腹が黒い従兄まで私が苦労しながら捕まえてあげたんですよ。寵愛をしなければ人ですか?」
正しい言葉であることを認めるのか、フェレルマン子爵はため息をついてうなずいた。
その一方で、何かずっと不審な様子だ。
「それでも・・・寵愛というには一定範囲を越えたようだが」
「絶対に違います。それは私がもっとよく知っています」
「養女には絶対になれない」と、イザベル夫人を食いつぶしていた声を思い浮かべながら、私はきっばりと話した。
「むしろ一定の線を絶対に越えられないようにするのは公爵様なんですよ。私が主題を知らないことをしたら、多分他の人のように不気味に急変するでしょうね」
「そうだね。二重人格だと分かればいい」
「二重人格というよりは・・・高い地位の人として表と裏が違うのは当然でしょう」
「とにかく、すごく気に入らないように」
フェレルマン子爵が眉をひそめてつぶやいた。
「まあ、とにかく他人の子だから、私の知ったことじゃないな」
彼は首を横に振りながら舌打ちをする。
「私と絡むことはないはずだから」
退屈な授賞と色々な演説が続き、少し疲れる時になってようやくハエルドン皇子が前に立つ。
「皆さんご存知だと思いますが」
彼は傲慢にあごを上げた。
「数日前、面白い対決が即興的に行われました」
私は一瞬、ハエルドン皇子の視線がフェレルマン子爵に届いたことを感じた。
フェレルマン子爵が不満そうに独り言を言う。
「相変わらずだな」
「え?」
「人が怪我をしたのに面白いなんて」
しばらくハエルドン皇子とフェレルマン子爵の冷たい覗線がぶつかり合う。
わずか数分前、社会生活を云々していた人が建てるのに適切な表情ではなさそうだった。
「実力の限界で皇室研究室を飛び出したフェレルマン子爵の助手、リチェ・エステルと皇室研究室のナタリー・イルター・ルウェリッチ令嬢がお互いの実力を競うことにしたのです」
私は呆れて鼻で笑った。
今このように公開的な場所で「実力の限界」を云々するとは、気が狂ったのかと思ってしまう。
フェレルマン子爵の腕を掴みながら、私はつぶやいた。
「完全にうわごとですね」
怒りをぶちまけると思っていたフェレルマン子爵は、意外と落ち着いていた。
「18年前のことだね、もう。記録はもともと残った者たちのものだ」
「・・・」
「どうせ娘を探すために出かけるのは私の選択だから何と騒いでもかまわない。後悔はないよ」
彼はまだ私とハエルドン皇太子の賭けの内容を知らない。
最大限劇的な喜びのために私たち皆が隠すことに合意したのだ。
それでも、こんなにハエルドン皇子が卑劣に出てくるとは思わなかった。
(関係ない)
私は静かに立ち上がり、考える。
(どうせ私が勝つのだから)
ハエルドン皇太子の案内に従って、私とナタリーはゆっくりと立ち上がり、人々の前にある壇上に立った。
皇帝と皇后、皇帝の側室が高いところから私たちを眺めている。
そしてその下では皇太子を一番上に置き、大貴族の代表が座っていた。
公爵のエルアンも皇太子のすぐそばで私を眺めながら目を輝かせている。
一つも不安ではないという表情で。
皇太子さまは、体面など一つもない表情で拍手をした。
「リチェ嬢!応援してるよ」
昨日、刺客に暗殺の脅威を受けた顔とは思えない。
「運動競技ですか?応援すればいいというわけではありません」
エルアンがぶっきらぼうに癇癪を起こす。
「それはそうだね?じゃあどうすればいいんだ?」
「黙っていればいいのです」
「そうだね、忠臣の言葉だから聞かないと」
「忠臣のようなことを言わないでください。とても気持ちが悪いです」
「もともと人は言葉ではなく行動で判断するんだって」
一体なぜあのように対話が流れるのか分からなかった。
エルアンはすぐに謀反を企てるような生意気な態度だったが、忠臣とは・・・・。
到底私が理解できる範囲ではない。
「それでは、それぞれ2日間担当していた負傷者を連れてくることにしましょう」
ハエルドン皇子があごを上げて言った。
「まずはリチェ・エステルが診た『エシアン・レイジ』から見てみましょう」
私の患者、エシアンはまだ一人で歩くには無理がある。
それでディエルが彼を支えながら上がってきた。
私はきちんと状況を説明する。
「ハリピヒキガエルの毒に中毒になったと判断し、イリテ試薬でできるだけ毒の排出に気を使いました。現在、意識も戻り、心臓の鼓動と呼吸も正常です」
確かに2日前に血を吐いて自分の体を支えられなかった時よりはるかに回復した姿に、人々がうなずく。
「通常、ヒキガエル科の毒は副作用が激しいため、慎重に扱う必要があります。まだ動きはあまり楽ではありませんが、このような方法で.一ヶ月ほど休憩を取れば完治するでしょう」
患者検証のため、ケインズ卿をはじめとする軍医数人がエシアンの状態を確認した。
心臓の鼓動と呼吸、基本的な小筋肉の動きなどを確認した彼らが、私の話が正しいという意味でうなずく。
「とにかく挙動は不便だということですね」
ハエルドン皇子は目を伏せて言った。
「完治は1ヵ月後に可能だということですね、そうでしょう?」
「はい」
「では、とにかく今完治はしていないのではないですかハリフィ・ヒキガエルの毒だと断言することもできないし」
「1ヵ月後には断言が可能でしょう」
私は淡々と答える。
いずれにせよ、トマソ症候群では決してなかった。
ハエルドン皇子は誠意なくうなずいて、再び人々に覗線を向けた。
「それでは、ナタリー令嬢が治療した負傷者を見てみましょう」
壇上の右側から彼女が担当した患者が出てきた。
「あり得ない」
ディエルの支えが必要だったエシアンとは異なり、彼女の患者はたくましく歩く姿が完全に回復した姿だった。
堂々と一人で立った彼を見て、人々がざわめき始める。
ナタリーは朗々とした声で言った。
「私はトマソ症候群と判断し、ヒリカ魔力治療で一時的に血液を中和しました。そして、ケシオ試薬を処方して2日以内に完治させました」
私の人生で数少ない当惑した瞬間。
確かにこの負傷者は、私があの時状態を交差点検した患者だった。
絶対にトマソ症候群ではなかったし、ナタリーが言ったように処方していたら、ヒリカ魔力治療をする時から喀血がさらに酷くなっただろう。
処方そのものを続けることができなかったはずなのに、どうしてあんなに完璧に回復させたのか分からない。
「患者をすり替えたわけでもないようだが・・・」
ケインズ卿と軍医は彼の状態を確認し始めた。
ナタリーの負傷者は、自分の健康を誇るように筋肉を自慢しながら、さまざまなポーズを取って見せた。
『あなたは負けるしかない。時間が経ってから、あの時ナタリー・イルター・ルウェリッチが貴族らしい慈悲を施したんだなと思って涙が出るでしょうね』
私は負けるしかないというその言葉を思い出して、下唇をぎゅっと噛んだ。
それでも医学に接する人なのに、医療研究室の仮面をかぶってごまかすとは思わなかった。
どうも怪しくて私が割り込もうとしていたところだった。
「ちょっと待って」
遠くからフェレルマン子爵がゆっくりと立ち上がる。
「ヒリカ魔力治療をしたって?」
ざわついていた人たちが静かになり、彼はゆっくりと前に進みながら言った。
「そしたらナタリー令嬢の言葉通り血液が中和されるだろうし・・・」
私はぼんやりと壇上に上がってきた彼を見る。
いや、私だけでなく、すべての人が久しぶりに姿を現したフェレルマン子爵を息を殺して眺めていた。
「注射器一つとアルコール綿をお願いしよう」
フェレルマン子爵は軍医の1人に手を差し伸べ、彼は素早くアルコール綿と注射器を差し出した。
私はフェレルマン子爵が自分の血を抜くのを見て口を開いた。
「まさか!」
「一時的に血液が中和されたのなら、今はどんな血液を入れても大丈夫だろうね、ナタリー令嬢?」
ナタリーの顔色が青ざめる。
その言葉に答えたのはケインズ卿だった。
「そうですね」
「じゃあ、私の血を入れても大丈夫だね。ちなみに私はE型だよ」
ナタリーとの対決は敗北に思えましたが、どうも怪しい・・・。
アルガの指摘に、ナタリーはどう反応するのでしょうか?