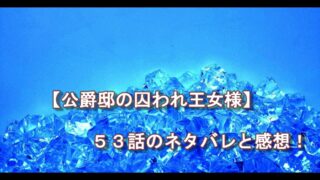こんにちは、ちゃむです。
「できるメイド様」を紹介させていただきます。
今回は186話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

186話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 王室騎士団⑥
まもなくポンティル男爵が非常に警戒心に満ちた表情でバルハン伯爵と共にマリーの前に現れる。
「連れてきました」
バルハン伯爵はちらりとポンティル男爵を見て言った。
「そんなに警戒する必要はない。武器も全然持っていないので」
「黙れ!ここがどこだと!」
バルハンはくすくす笑う。
「帝国近衛騎士は武器もない者を恐れるのか」
「こいつ・・・」
ポンティル男爵は歯ぎしりしたが、軽挙妄動しなかった。
バルハン伯爵は王室騎士団の団長で、事実上クローヤン王国の最強騎士。
ポンティル男爵もトップクラスの騎士だったが、バルハン伯爵には一枚及ばなかった。
キエルハーンやラエルなら彼を相手にできるだろうが。
「いったいお前が書記官だなんて、どういう下心だ?」
「私は文章が上手だ。十分に書記官の職責を遂行する能力がある」
「そういう意味じゃない!」
バルハンは走り回るポンティル男爵から首を回してマリを見た。
そしてひざまずいて礼をする。
「セルアン伯爵家のバルハンです」
その劇例にポンティルは目を丸くした。
まるで王族にするかのように、いや、忠誠を誓った主君にするかのように、礼儀正しい口調だ。
マリはため息をつき、ポンティル男爵に話しかける。
「男爵、申し訳ありませんが、しばらく外でお待ちください。お願いします」
ポンティルは出ないつもりだったが、マリが繰り返し頼むと仕方なく出て待機した。
二人だけが残るようになると、マリがバルハン伯爵に尋ねた。
「私も気になりますね。何を考えているんですか、書記官だなんて」
マリは不思議そうな表情で額にできた傷跡を見る。
熊も素手で捕まえそうな強靭な印象で書記官を志願するなんて?
(私に従うことにしたの?)
それは違うようだ。
彼の目つきには依然として混乱が満ちていたから。
しかし、彼の瞳には以前にはなかった光が浮かんでいたが、それは罪悪感だった。
(罪悪感?なんで?)
その瞬間、バルハンが再びひざまずく。
単に礼を言うのではなく、まるで罪を告げるかのように頭までぐっと地面に下げて。
「すみません、殿下!」
「伯爵?急にどうしたの?」
マリはびっくりして彼を呼んだ。
「やはり殿下の意思に従うことはできません。いくら考えても、王家を再建しなければならないという考えは変わりません」
彼の声には苦しみが満ちていた。
マリは忠誠心と王室の再建に対する彼の信念の衝突の間で骨身を削るような苦痛を感じた音を察することができた。
「それで・・・本当に不忠極まりないことですが、あえて一つをお願いします!私をそばにとどまり、殿下を見守る時間を与えてください」
「・・・」
「殿下の道が本当に正しいと確信したら、その時は殿下に従います!お願いします!」
彼は再び頭を地面にぶつける。
「あえてこのようなお願いをするのは申し訳ない」という態度だった。
マリは急いで彼を起こした。
戸惑ったが、彼女としては反対する理由がない。
いや、むしろ彼女が頼みたいことだった。
「お立ちなさい、伯爵。むしろ私の方がありがたいです」
「殿下?」
「私にチャンスをくれたわけですから。ありがとうございます。がっかりさせないように、私は最善を尽くします」
マリが彼に手を差し出した。
彼女が差し出した手を見たバルハン伯爵の瞳が再び揺れる。
「だから伯爵も私を助けてください。これからよろしくお願いします」
そのように紆余曲折の末、王室騎士団の団長であるバルハン伯爵がマリの下に入ってきた。
もちろん彼は彼女に完全に忠誠を捧げることにしたわけではない。
これからのマリの行動によって、彼の決心は完全に変わるだろう。
それでも彼が彼女を見守ると決心したことだけでも途方もない意味があることだった。
彼女がすることによって心を変える可能性が十分にあるという意味だから。
つまり、クローヤン地方の安定の区分稜線を越えたのだ。
「もうほぽできた」
暗い夜、マリは月明かりを眺めながら考える。
もう本当にほとんどできた。
もう少し努力すれば、クローヤン地方は完全に安定するだろう。
王家の再建を望む人たちは、志を果たすことができず残念だと思うかもしれないが、それは当事者である彼女が望んでいたことではなかった。
「重要なのは王家の再建ではなく、王国民が幸せを見つけることだから」
何よりもマリは王家再建だけが王国民を幸せにする道だとは思わなかった。
彼女は自分のやり方で君主国のために最善を尽くすだろう。
そのように考えを整理したマリは窓の外の遠くに向かって視線を向ける。
ラエルのいる皇居の方角へ。
「会いたいです、陛下」
最近、色々なことが多いからだろうか。
早くすべての仕事を終えて帰って彼の胸に抱かれたかった。
「愛・・・しています」
彼を思い出すと懐かしい気持ちがこみ上げてきた。
とても会いたくて、訳もなく涙が出そうだ。
「もう少し頑張ろう。もうすぐだよ」
マリは冷たくなった目元をさっと拭きながら首を横に振った。
その時、部屋の外でノックの音が聞こえた。
「誰だろ、こんな時間に?」
不思議そうな表情でドアを開けると、ポンティル男爵が上気した顔で立っていた。
「男爵様?何の用事で?」
「招待状が届いたので、急いでお伺いしました」
「招待状ですか?」
マリは首をかしげた。
だが、男爵が渡した招待状の文章を見た瞬間、マリはなぜ彼がこの時間に急いで訪ねてきたのか知ることができた。
「皇室の紋章!」
古風に飾られた招待状には、東帝国の皇室の紋章が刻まれていた。
ラエルが送ったのは明らかだ。
彼女を皇居と呼ぶ招待状なのだ! .
マリは急いで招待状を開いた。
・
・
・
私の大切な君へ。
今度の帝国誕生宴会に参加して宴会を輝かせてほしい
・
・
・
「誕生宴会?」
そういえば、帝国は年中最大の行事である「誕生宴会」が開かれる時期。
「でも、なんで急に?」
マリは一瞬疑問に思った。
全く予想できなかった招待だったのだ。
(何か特別な理由があるの?それとも予備皇后だから?)
実際、礼法上、当然参加するのが正しいことではある。
予備皇后である彼女は、皇帝ラエルとともに誕生宴会の主人公のようなものだからだ。
しかし、彼女は今、クローヤン地方から身を引くのが難しい状況。
ラエルの普段の性格を考慮すれば当然配慮してくれたはずなのに、なぜあえて招待状を送ったのか分からなかった。
(もしかして本当に何かあったのか?)
マリは訳もなく不安になり、顔色を整える。
マリの不安のように、ラエルは何の理由もなく彼女を呼んだのではなかった。
数日前、東帝国の皇居で起きたことだ。
ラエルは重い表情を浮かべていた。
彼は彼女のことを思っていた。
敵地同然のところに自分の命よりも大切な彼女がいるので、一日一日が燃えていく心情なのだ。
毎朝、目を覚ますたびに、もしクローヤン地方から悪い知らせが飛んでくるのではないかとはらはらしていた。
そして、彼の心を苦しめるのはそれだけではない。
「マリ、私はあなたを一体どうすればいいんだ?」
その時、ちょうどノックとともに聞き慣れた声が聞こえた。
「お上がりです、陛下」
その音にラエルの顔はこわばった。
「失礼します」
すぐにオルンがドアを開けて入ってくる。
ラエルの表情はさらに硬くなった。
「何の用だ?」
「ご存じではありませんか?」
オルンも同様に硬い表情だ。
二人はしばらく黙ってお互いを見つめ合った。
「もしこの前のような用事なら、私はもう言うことがない。帰るように」
ラエルは眉をひそめた。
「マリがクローヤン王国の独立を画策しているかもしれないなんて。そんなとんでもない話なんて聞きたくない」
彼の口から出た話は耳を疑うほと驚くべきものだった。
マリがクローヤン王国の独立を画策しているなんて?
とんでもない内容だったが、オルンは重く口を開いた。
「マリがモリナ王女である可能性は陛下も十分にご存じではありませんか?」
オルンは最近、クローヤン地方を集中的に調査し、いくつかの手がかりを追加で得た状態だ。
そして、その手がかりはすべて一つの可能性を示している。
マリはモリナ王女かもしれない。
いや、可能性ではなく、この程度の手がかりなら、マリはモリナ王女と見なければならなかった。
「単に彼女がモリナ王女であることが問題ではありません」
オルンは重い声で口を開いた。
「クローヤン王国で彼女に対する支持率があまりにも高くなりました。単に少し高いレベルではなく、ほぼ圧倒的なくらいです。以前のクローヤン王国の王たちも、これほどの支持は受けていないはずです」
ラエルは眉をひそめ、オルン側の言葉を聞く。
「一般的には、彼女への支持が高いことは何の問題にもなりません。むしろ歓迎すべきことです。しかし、他の人ではなく、彼女なので、これは深刻な問題になる可能性があります」
オルンはしばらく口をつぐんだ後、深刻な顔で話した。
「もしマリがモリナ王女なら、クローヤン王国は彼女を女王に推戴し、すぐにでも独立しようとするでしょうから。それがまさに問題です」
ゾッとするような話だ。
マリがモリナ王女なら、クローヤン王国は一気に彼女を中心に団結するだろう。
もちろんマリ本人にはそんな考えが塵ほどもなかったが。
「そんなことを言っているのか?マリがそんな考えを持っているはずがないじゃないか?」
ラエルはこのような話をすること自体が不快そうな顔をした。
「それは私が確信する」
彼の固い言葉に宰相のオルンはため息をつく。
「もちろん私もヒルデルン子爵を信じています。しかし、この事案はそのように考えて見過ごす内容ではありません。もし彼女が別の心を抱くなら、帝国に致命的な結果をもたらすでしょうから」
オルンも彼女を疑いたくなかった。
彼女が今まで帝国のためにした献身は嘘ではなかったからだ。
マリはラエルと帝国のために何度も大きな危険を冒した。
にもかかわらず、この問題を持ち出す理由は、あまりにも帝国に致命的な事案だったからだ。
クローヤン地方が独立すればすぐに起きるかもしれない西帝国との戦争で、東帝国は非常に不利な立場に置かれることになる。
無条件に防がなければならない。
「また、疑わしい状況がいくつかあります。先日、ヒルデルン子爵は誰にも知らせずに王室騎士団のバルハン伯爵と密会を行いました。その時、二人がどんな会話をしたのか知っている人がいません」
以前、マリが密かにバルハン伯爵に会ってきたことを言うのだ。
ラエルは激しく首を横に振る。
「彼女が不敏な話をしたはずがない」
「私もそう信じたいです。しかし、誰も知らないことです」
二人の視線が再び空中で合った。
ラエルは強い目つきでオルンを睨み、彼は避けなかった。
「それだけではありません。最近は王国民を対象に騎士の兵力と官吏を募集しているそうですね。融和のための試みだとは思いますが、あまりにも偶然です。もちろん私も知っています。ただの仮定です。しかし、万がーでもそのようなことが起きれば、現在四面楚歌の危機に包まれている東帝国としては手に負えない危機を迎えることになるでしょう」
オルンの言葉は正しかった。
機密なので一般人に広がることはなかったが、現在東帝国は前例のない危機に直面している。
いずれも西帝国のヨハネフ3世のためだ。
今、ラエルはその危機に対応するためにマリのところに行くことができず、皇居に留まっているのだった。
「私はヒルデルン子爵の総督位を解任し、直ちに本国に送還して尋問しなければならないと思います」
しばらく二人の間に息が詰まるような沈黙が流れる。
ラエルは力強い声で話した。
「ただの策略にすぎない。君の話はただの推測に過ぎず、何の証拠もない」
「ですが陛下・・・」
「もういい。私はこれ以上この話をしたくない。他のことはさておき、私は彼女を信じ亭る」
しかし、今回だけは引き下がれないという顔をした。
「陛下、どうかもう一度お考えください。帝国の運命が左右される可能性がある問題です」
「・・・」
ラエルはしばらく返事をしなかった.
オルンは熱心な目でラエルを見る。
「マリがそんなはずがない。こんな話をすること自体が彼女に申し訳なくて不快なほどだ」
「陛下」
ラエルは続けた。
「しかし、私の信頼を他の人にまで強要することはできない。だからこのようにする」
ラエルはゆっくりと息を吸った。
「ヒルデルン子爵に直接聞く。まもなく開かれるる帝国誕生宴会の時、彼女を皇居と呼ぶように」
ラエルは彼女に直接聞くことにした。
彼女を疑っているからではなく、むしろ彼女を信じているから。
これまで首を回してきた彼女に対する真実に直接向き合うことに決めたのだ。
バハルンがとりあえず味方?になりました。
このタイミングでの招待状。
ラエルからの直接の質問に、マリはなんと答えるのでしょうか?