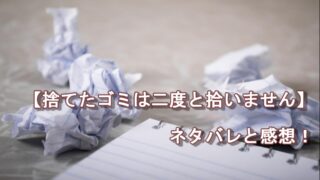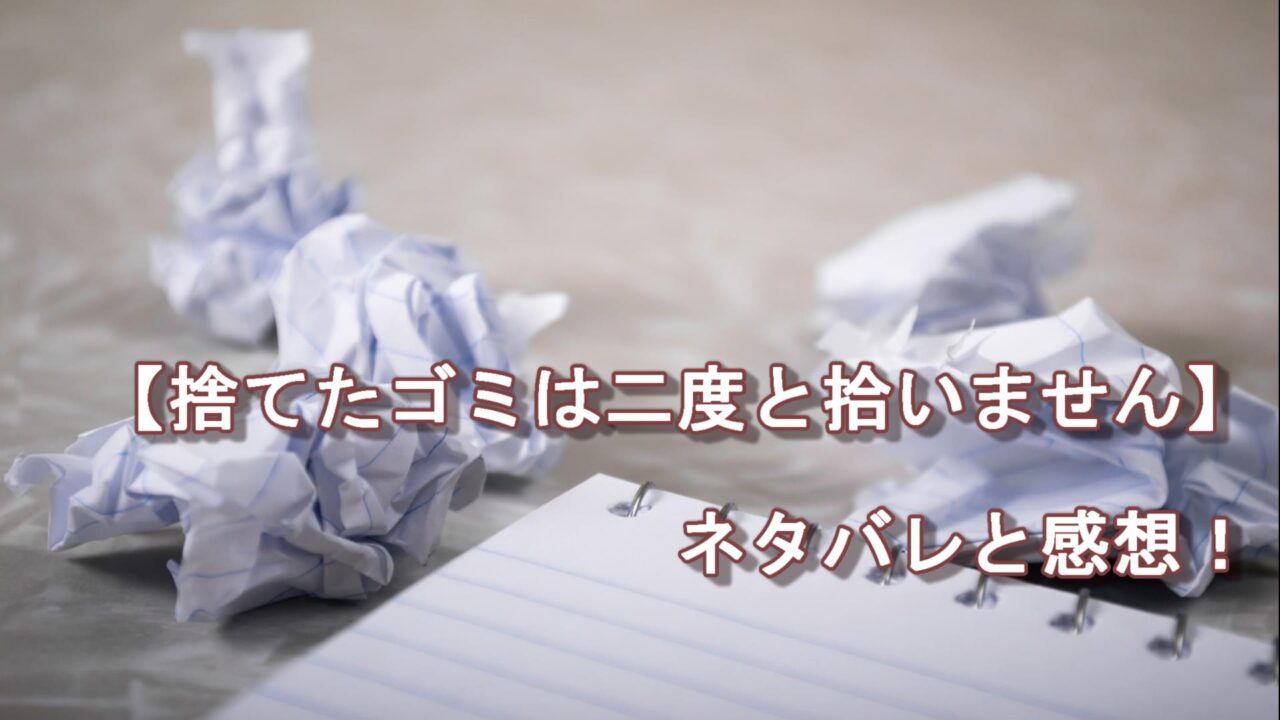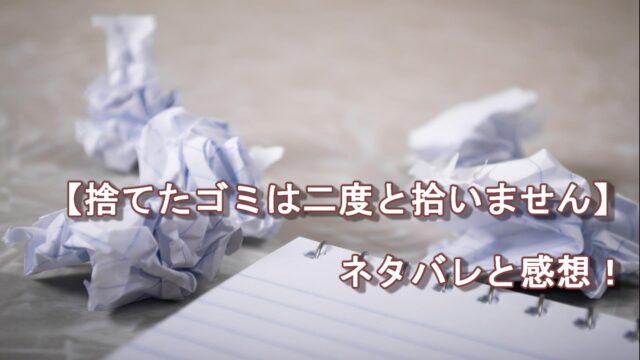こんにちは、ちゃむです。
「捨てたゴミは二度と拾いません」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

2話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- プロローグ②
ウィリオット公爵夫妻が亡くなって3年目のある日、領土拡大の野心を持つ皇帝が大規模な遠征を宣言し、フィレンは戦場に向かうことになった。
すぐに終わって戻ってくると思っていたが、戦争はさらに6年続いた。
長い戦争は多くの人々を疲弊させ、その中には私も含まれていた。
私は公爵夫人としての役割に加え、公爵不在の間の公爵代理としての責任も果たさなければならなかった。
空いた役割を補うために、私は忙しく走り回らなければならなかった。
領地を平穏に保つためにやるべきことは山ほどあったが、問題はフィレンが旅立って間もなく大飢饉が訪れたことだ。
穀物の価格が数倍に跳ね上がり、それに耐えられず飢えに苦しんで命を落とす人々が次々と現れた。
特に幼い子供たちが多く亡くなり、生存のための犯罪も頻繁に発生した。
彼らを救おうと、私は公爵家の倉庫に蓄えられた大量の食糧を放出した。
その結果、私はしばらくの間、薄いスープと硬いパンしか口にできなかった。
ミサや他の使用人たちはこの状況を心配していたが、私は気にしなかった。
食べ物にすら手が届かず餓死する人々が多い中、自分が食べられるだけでも感謝していた。
そのようにして大飢饉をかろうじて乗り越えた後、今度は伝染病が発生した。
私は伝染病を克服するために、ウィリオット公爵家の資産を使い、医者や神官を呼び寄せた。
膨大な額が一度に流出し、公爵家の財政が一時的に揺らいだものの、これまで私に与えられた品位維持費を節約していたおかげで、どうにか乗り越えることができた。
こうして6年間、公爵夫人としての役割と、実質的な公爵の代理としての役割を果たしながら、長年続いた戦争はついに終わりを迎えた。
これは、先代皇帝が崩御し、新たな皇帝が即位したことで、長引いていた戦争に終止符が打たれたからだ。
フィレンが帰ってくるという手紙を受け取った私は、6年ぶりに花嫁のように身支度を整えた。
いつも身に着けていた質素なドレスを脱ぎ、優雅で華やかな装いに身を包んだ。
華やかなドレスをまとい、化粧も普段とは違って濃く仕上げ、さまざまなアクセサリーを身に着けていく。
すべての準備を終えた後、鏡に映る自分の姿はとても不自然に感じられた。
赤く塗られた唇をきゅっと引き上げて明るく笑ってみたが、やはり不慣れな感じがする。
似合わない服を着ている気分だった。
普段着ている落ち着いた色の控えめなドレスの方が、自分にはよく似合うように思えた。
「本当に美しいです、お嬢様。」
「そうです!天から舞い降りた天使のようです!」
しかし侍女たちの褒め言葉に、私は恥ずかしさから手を振って彼女たちを止めた。
「もう、やめて。恥ずかしいわ。」
私は頬を赤らめ、手を軽く振ると、皆が明るい笑顔を浮かべた。
フィレンを心から愛しているわけではなかったが、それでも彼は私の夫になる人だ。
そのせいだろうか。
フィレンが帰ってくるという知らせに胸が高鳴った。
心が雲の上を歩くようにふわふわして、足がそわそわと落ち着かない。
まるで思春期の少女に戻ったような気分だ。
高鳴る気持ちは、遠くにフィレンが率いる騎士団が見えたときにさらに大きくなった。
先頭で黒馬に乗る男性、それがフィレンだった。
まだ距離はかなりあったが、私は一目で彼だとわかった。
距離がだんだん近づき、みんなが彼がフィレンだと確信できるようになった頃、私は喜びのあまり手を振った。
「フィル……。」
そう言おうとしたが、フィレンの腕の中に他の女性がいることに気づき、言葉を失った。
他の女性。
彼が他の女性を抱いているなんて。
夢にも思わなかった事実に頭が真っ白になり、まるで冷水を浴びせられたように心が乱れた。
私は呆然としたまま、フィレンと彼の腕に抱かれている女性を見つめた。
距離が近づくにつれ、フィレンの腕の中の女性の姿がはっきり見えてきた。
日差しの中で輝く白金色の髪が非常に美しかった。
白磁のように滑らかな肌は、その女性が普通の身分の者ではないことを示していた。
私の視線がその女性を追いかける中、視線が止まったのは痩せた腕と華奢な脚から飛び出した豪華な衣装だった。
座っているからそう見えるのだろうと思いたかったが、腹部がかなり膨らんでいた。
まさかあの女性が……。
「ご主人様の腕の中にいる女性、妊娠しているのではないですか?」
隣にいた侍女が私の考えを代弁するように口にする。
他の使用人たちも同じ考えなのか、ざわめき始めた。
「どうしてご主人様が妊娠した女性を連れてくるの?」
「まさかあの女性がご主人様の子供を……。」
「皆、静かにしなさい!」
ミサの一喝に、全員が口をつぐんだ。
「そんなはずありません。」
ミサは不安で震えている私に向かってきっぱりと言った。
「ご主人様がそんなことをなさるはずがありません。何か誤解があるに違いありません。」
誤解、本当にそうだろうか。
不安ながらも、私の直感はミサとは異なり、あの女性がフィレンの子供を宿していると確信していた。
それでなければ、フィレンがあの女性を腕に抱えたまま戻ってくる理由があるだろうか。
「はあ。」
思いもよらなかった事実に、私は思わず笑いながら頭を抱えた。
本当にあの女性がフィレンの子供を宿しているとしたら、私はどう対応すればいいのだろう?
これからどんな振る舞いを見せればいいのだろう?
大勢の目が私に向けられる中で、あの女性の髪を掴んで怒りをぶつけるべきなのだろうか?
それとも、気高い貴族夫人のように余裕を装い、女性を見なかったことにするべきなのだろうか。
いや、それ以前に私にそんな資格があるのだろうか?
私はフィレンの正式な妻ではなく、ただの婚約者に過ぎない。
周囲では既に私がウィリオット公爵夫人であるかのように扱われていたが、私の姓はまだ「テベサ」のままだった。
レイラ・ウィリオットではなく、レイラ・テベサ。
そんな私が、フィレンが連れてきた女性に対して何かを言える立場にあるのだろうかと疑問が湧いてきた。
婚約者という立場では多少の発言権はあるかもしれないが、果たして政府高官のように女性を非難できるだろうか。
だからこそフィレンにどんな言葉をかけるべきなのか分からなかった。
彼にどんな顔をして会うべきかも見当がつかなかった。
衝撃を受けた私はいろいろな考えにとらわれて悩んでいるうちに、気づけば私たちの目の前にフィレンが馬から降りて近づいてきた。
あの青さが完全に抜けた顔立ちは、鋭さと洗練さを誇っていた。
6年ぶりに会った彼は完全に大人の男になっていた。
「こんな……。」
しかし、彼の唇に浮かぶ微笑みは以前のままだった。
フィレンは以前と同じように穏やかに微笑み、私の後ろに立っている使用人たちを見渡した。
「僕がいない間に、みんなおしゃべりになったようだね。」
フィレンの視線が最終的に止まったのは私だった。
彼は首をかしげながら、相変わらず茶目っ気のある声で言った。
「レイラ、まさか6年の間に臆病者になったわけじゃないよね?」
「……そんなわけないでしょ。」
やっと正気を取り戻した私は、かすれた声を絞り出しながら答えた。
「ちょっと驚いただけ……。」
「何が?」
彼は本当に知らずに聞いているのだろうか?
それとも私を試しているのだろうか?
それも違うなら……まさかあの女性が彼の子を身ごもっているわけじゃないだろうか。
どうすれば最後の瞬間を理解できるのだろうかと考えた。
いや、そうであることを強く願っていたけれど、フィレンがあの女性を連れてきた理由は説明されないままだ。
それに、彼女が彼の腕の中に抱かれ、彼の馬に乗せられてやってきた理由が分からなかった。
私は目を凝らして、フィレンの馬に乗っている女性を見つめる。
遠くから見たときはそこまで目立たなかったが、近くで見るとその女性はかなり美しい人だった。
青い瞳がまるで宝石をちりばめたように輝いていた。
女性は派手なドレスではなく、普通のリネンのワンピースを着ていたが、それでも華やかに装った私よりも美しく見えた。
その事実に、自分の疑念と敗北感を覚えた私は、そっと手を握りしめた。
私は無理やり視線を動かした。
その女性を見たくないと思いながらも、不思議なことに女性から目を離すことができなかった。
もしフィレンがあの女性を愛人にしたのだとしたら、なぜ彼女だったのか納得がいくほど美しい女性だった。
「ずっと馬に乗っているのは疲れるだろうから、これで降りてくれ。」
フィレンはそれ以上何も言わず、丁寧で優しい手つきで女性を馬から降ろす。
女性は恥ずかしそうに頬を赤らめながらフィレンの腕の中に身を委ねていた。
馬から降りた後も、そのままフィレンにしがみついていた。
フィレンはそんな彼女を突き放すことなく、むしろさらに優しく抱きしめていた。
「主人がどうして……。」
「お嬢様を置いてそんなことをするなんて、許されるはずがない。」
二人の親しげな様子に、侍女たちや使用人たちは小さく憤慨した。
先ほどまで「そんなはずがない」と否定していたミサまでが「馬鹿げている」と主人に向かって鋭い言葉を吐いた。
彼女と使用人たちの言葉は叱責を受けるべきかもしれなかったが、私も同じように感じていたため、何も言わなかった。
むしろ、私が言いたかったことを代弁してくれた彼らを心の中で称賛した。
たとえ私とフィレンが愛のない婚約関係だったとしても、婚約者である私の前であのような行動をとるべきではない。
嫉妬を受けても仕方がないほどだ。
今すぐにでも彼の襟元を掴み、何をしているのかと問い詰めたかった
あの女性は誰で、彼の子供を身ごもっているのかを叫びたかったが、不思議なことに口を開くことができなかった。
怒りに震えながらも、蜂に刺されたように口を閉ざし、悔しさで震えていた。
怒りを込めた目で彼をじっと見つめることしかできなかった。
そんな私の視線に気づかなかったのか、フィレンは無表情で自分の腕に抱えられた女性に優しく語りかけた。
「長旅でとても疲れただろうから、部屋に戻ってゆっくり休んで体をいたわるといい。」
「日当たりのいい部屋がいいです。」
女性が細く弱々しい声で要求すると、フィレンは一瞬考え込み、ミサに向かって言った。
「ミサ、この女性を2階の東側、廊下の端にある部屋に案内してくれ。」
その言葉に、ミサの目が見開かれた。
他の侍女たちや使用人たちも驚きで口を開けた。
東側北の端の部屋。
それはウィリオット公爵夫人が使う寝室だ。
公爵夫人の役割を代行している私でさえ、その部屋を使ったことはなく、たとえ皇帝が使いたいと言っても許されない場所だった。
そんな場所を使うなどという皇帝もいるはずがないが。
それなのに、その部屋を正体不明の女性に案内すると言うのだから、皆が驚くのも無理はない。
あまりのことに茫然としていたフィレンではなかったが、私がその視線を捉え、彼が無知であることを悟って彼に声をかけた。
「フィレン、その部屋は公爵夫人の部屋よ。」
私の言葉にフィレンは私を振り返った。
目には疑問が浮かんでいた。
「それで?」
やっぱり知らなかったのか。
そう思うと、漠然と感じていた不快な気持ちが少しだけ和らいだ。
「公爵夫人の部屋は誰でも使える部屋じゃないの。ただ公爵夫人だけが使えるの。」
「でも父上は使っていた。」
「それは公爵閣下だから……。」
「それに君も使った。」
「それは仕事をするためで仕方なかったの。」
私の部屋で仕事をしたいと思っても、当時邸宅の帳簿は公爵夫人の部屋に保管されていて、それを外に持ち出すことは厳しく禁じられていた。
だから仕方なくそうしたし、公爵夫妻も了承していたけど――。
「そして、あそこではただ仕事をしただけで、そこで眠ったわけではない。」
公爵夫人は自分がいないときに使っても良いと言っていたが、それは例外ではなかったようで、無条件に自分の部屋で寝た。
「だから、あの女性を公爵夫人の部屋に入れるのはダメよ。」
「でも、あの部屋は日当たりがいい。」
「日当たりのいい別の部屋もあるわ。」
「あの部屋ほど良くはない。」
核心を突くその言葉に私は口を閉ざし、フィレンは深いため息をつきながら不満げに言った。
「どうせ誰も使わない部屋を少し使うだけなのに、こんな小言を聞く羽目になるとは思わなかった。」
「小言ではなく、この邸宅の規則よ……」
「邸宅の規則を決めるのは、この邸宅の主人だ。」
フィレンはこれ以上聞きたくないというように、私の言葉を遮り、高圧的で権威的な目つきで私を見つめた。
「そして今、この邸宅の主人は俺だ。」
「……」
「賢いお前なら、どういう意味か分かるよな?」
どうしようもなかった。
彼が無条件にあの女性を公爵夫人の部屋に入れるつもりだという意味を。
反対したくても、それを阻むだけの理由が私にはなかった。
邸宅の規則を決めるのは邸宅の主人だ。
主人がそうすると言うのなら、どうやって止めることができるだろう。
たとえ私が本物の公爵夫人だったとしても、止めることはできなかっただろう。
私が沈黙を保つと、それを肯定と受け取ったのか、フィレンはミサに命じた。
「ミサ、彼女を東側北棟の一番奥の部屋に連れて行け。そして滞在中、彼女が不自由しないように誰かをつけてやれ。」
「かしこまりました。」
別の機会なら、これは明らかに騒動を招く命令だった。
しかし、これ以上の争いを望まなかったのか、ミサは素直に従った。
彼女は私を一瞥し、女性を連れて邸宅の中へと入っていった。
本当にあの女性を公爵夫人の部屋に入れるのか。
どうすることもできず、失笑が思わず漏れた。
私は引きつる顔をなんとか緩めようと努め、美しく塗られた唇だけを噛みしめた。
その結果、見事に彩られた唇が無意味に歪んでしまった。
「怒っているのか?」
フィレンは申し訳なさそうな様子もなく、普段と変わらない口調で尋ねた。
どうやら自分が何か悪いことをしたという自覚は全くないようだ。
ただ、公爵夫人の部屋に他の誰かを入れるべきではないということを知らなかったのだ。
それを知らなければ、どうして責められるだろうか。
そんな相手に怒りをぶつけても仕方がないので、私は必死に怒りを抑えた。
「……いいえ。」
私の返答に使用人たちは小さくため息をつき、フィレンは平然とした様子で愛馬のたてがみをなでていた。
「そうだな。この程度のことで怒るわけがないだろう。」
「……。」
「じゃあ、夕食のときに会おう。今は疲れているから少し休みたい。」
フィレンは私の肩に手を置き、それから邸宅の中へと入っていく。
フィレンが姿を消した後も、私は呆然と立ち尽くしていた。
すると、侍女が私の顔色をうかがいながら慎重に声をかけてきた。
「お嬢様、大丈夫ですか?」
「……大丈夫じゃないと言ったら、何か変わるの?」
「お嬢様……。」
侍女の声に慌てた私は、気まずさが押し寄せた。
怒りを我慢するなら最後まで我慢すればいいのに、思いがけず怒りを爆発させてしまった自分が恥ずかしかった。
自嘲しながら、私はそっと髪をまとめていたピンを外した。
「ただの一言よ。私は大丈夫。」
他の女性を連れてきた婚約者によく見られようと、早朝から起きて美しく着飾った自分が馬鹿馬鹿しく思えた。
「大丈夫だから気にしないで。それより片付けて夕食の準備をしよう。」
本当は何もしたくなかった。
全てを放り出して部屋に閉じこもり、涙に任せて感情を吐き出したかった。
でも、そんなことができる立場ではなかった。
私はフィレン・ウィリオットの婚約者であり、仮の公爵夫人というか弱い立場が足枷となり、感情を飲み込んで無理やり動かなければならなかった。